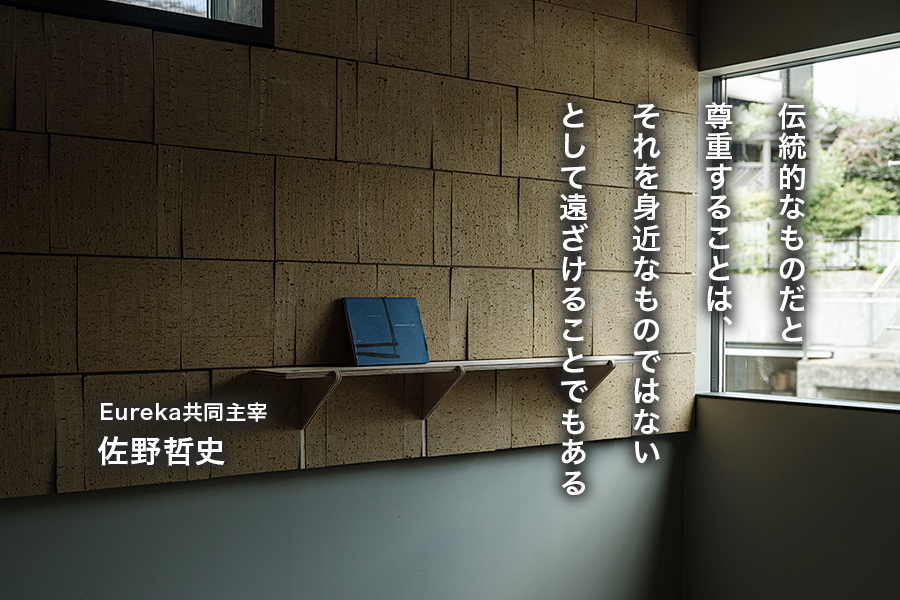和蘭の瓦(1) 甍のつらなるオランダの街並み(藤田悠/東京工業大学環境・社会理工学院建築学系博士後期課程)

瓦のある風景
> 「甍のつらなる大都市の渦 わき立ちこめる霧の中…」
(作詞: 北川冬彦/作曲: 高田三郎)
自分と瓦との接点を探すうち、母校の校歌の一節が不意に頭をよぎった。中学に入ってすぐの音楽の授業で甍(いらか)というのは瓦屋根のことだと教わり、それが大都市という語と並ぶとはどういうわけかとひとり不思議に思ったのを覚えている。瓦屋根が都市化を連想させる時期がかつてあったのだろうと頭で理解はできても、中学生の自分にとっては瓦自体がほとんど馴染みのない存在であり、ましてやそれが「つらなる」といわれても具体的にイメージすることができなかったのだ。しかし、そんなふうにものを知らなかった筆者も、中学入学から十余年後思いがけない場所で甍のつらなる風景との縁を得る。留学のため束の間オランダに滞在した時のことである。
オランダの街並みといえば、縦に長い煉瓦壁の建物が運河に沿って隙間なく並ぶ様がよく知られている。これらはカナルハウス(蘭: Grachtenpand)と呼ばれる形式の住居で、間口の狭い土地に床を積んだ結果として、前述のような縦長の立面がうまれる。都市によって微妙な差異こそみられるが、オランダを代表する風景のひとつといっていいだろう。アムステルダムのように商業の発展した都市では立面最上部の破風(蘭: Rolwerkgevel)を思い思いに飾ったものが多くみられ、この装飾がしばしば屋根よりも高くのびるためにどうしても煉瓦壁の印象が強いかもしれない。だが、よくよく見てみると、その背後に控える屋根はほとんどの場合瓦で葺かれている。

他方、ひとたび都市部を出ると、カナルハウスとは打って変わってずんぐりとしたプロポーションの住居が目立つ。水路の走るだだっ広い平原とこのような建物の組み合わせもまた、干拓の国オランダらしさを感じさせる風景といえる。雨が多く風も強いオランダでは50度から60度もの屋根勾配が必要とされており、平面にゆとりのある建物ほど立面全体に占める屋根の割合が大きくなりやすい。それゆえ、伝統的なファームハウスのような郊外の建物では屋根が重厚な存在感を放っていて、それらの多くもまた瓦葺きだ。

屋根がパイで飾られる
今回改めて勉強するまで知らなかったことだが、オランダにおける瓦の歴史はたいへん長く、少なくとも4世紀にまで遡る。その頃使われていたのは平らの牝瓦(めがわら)の継ぎ目を半円筒形の牡瓦(おがわら)で覆うローマ帝国式の瓦で、これが10〜12世紀頃まで使用されていたという。その後、中世に入り火災対策として家屋の草葺きが規制されるようになると火に強い屋根葺き材である瓦の重要度が高まり、14世紀以降オランダ独自の瓦が開発されるようになる。そのひとつひとつをここで紹介することはできないが、16世紀前半には牝瓦と牡瓦を一枚で兼ねるHolle Pan(波型瓦)が登場する。これを垂木上の桟に引っ掛ける構法によって、オランダの気候に対応した急勾配屋根も比較的容易に葺けるようになった。
1559年にピーテル・ブリューゲル(Pieter Bruegel; 1530頃-1569)により描かれた『ネーデルラントのことわざ(蘭: Nederlandse Spreekwoorden)』では、画面左手にファームハウス風の家屋が描かれ、その屋根の一部に大胆にもフラーイ(パイのようなオランダの菓子)が貼りつけられている。これは裕福な様子をあらわすことわざ “Daar zijn de daken met vlaaien bedekt(屋根がフラーイで飾られている)” をユーモラスに具象化したものだが、フラーイのないその他の屋根面は草葺きではなく瓦葺きである。これは1550年代にはすでに瓦が標準的な屋根葺き材と認識されていたことを示すといえるかもしれない。(このことわざが瓦とフラーイの色や大きさの類似性を前提とする洒落だとすれば、そのこと自体、当時の人々の瓦に対する親しみを反映しているようにも思われるがどうだろう。)

また、1661年にヨハネス・フェルメール(Johannes Vermeer; 1632-1675)により描かれた『デルフトの眺望(蘭: Gezicht op Delft)』でも、柔らかな朝日に照らされた瓦屋根が運河の向こうに見える。瓦とオランダの街並みとは歴史的にみても切っても切れない関係にある。

オレンジと黒の波
さて、フェルメールが題材とした街デルフトは、オランダ南部、ハーグとロッテルダムの間に位置するこぢんまりとした古都であり、画家自身が生涯を過ごした生まれ故郷でもある。先の絵画に描かれた地域は現在では旧市街と呼ばれ、往時の美しい街並みを今に残す。その中心部にある新教会(蘭: Nieuwe Klerk)の鐘楼にのぼると、フェルメールが描いたオレンジと黒の瓦が混ざり合う屋根並みを一望することができる。
このふたつの色の違いは主に工程の違いによるもので、鉄分を含む粘土を最後まで外気に通じた窯で焼成すると酸化鉄(Ⅲ)によりオレンジの瓦ができるのに対し、窯の温度が最も高くなったタイミングで給気を抑えると還元反応により酸化鉄(III)鉄(II)が生成し黒くなる。原理としては日本の素焼き瓦といぶし瓦と同じといえるだろう。

現在オランダで一般的に使われる瓦はOpniew Verbeterde Holle Pan(さらに改良された波型瓦)というもので、原型を辿ると16世紀前半に誕生したHolle Pan(波型瓦)に行き着く。これは日本で地瓦としてよく用いられる桟瓦に同じく、波型の断面をもち対角二隅が切り欠かれたものである。
実はこのような形状の瓦がみられる国は、ヨーロッパからアジアにかけてオランダ・インドネシア・日本にほぼ限定されるらしい。日本の桟瓦は、明暦の大火後の1674年頃に近江三井寺の瓦師西村五郎兵衛正輝(のちの半兵衛)により発明されたといわれる(オランダの技術が影響した可能性の是非については参考文献に詳しい)。Holle Panがオランダの急勾配屋根の瓦葺きを可能にしたように、日本の桟瓦も、頑強な構造を持たないふつうの建物における瓦葺き普及のきっかけとなった。つまり、かなり大掴みにいってしまえば、オランダと日本では17世紀以来よく似た瓦が使われてきたことになる。筆者がオランダで目にした甍のつらなる街並みは、日本のそれと同じ波のもとに生まれた。

ボキャブラリーとしての瓦
既に述べた通り、オランダの急勾配屋根は建物の立面に大きくあらわれる。したがってオランダでは、ともすれば日本以上に、瓦が建物の外観を決する重要な要素のひとつとして意識されてきたのではないかと思う。後代の建築家らの創作に瓦を巧みに用いた表現をみることができるのも、そのあらわれではないだろうか。
20世紀初頭のオランダで近代芸術運動の一派として興ったアムステルダム派(蘭: Amsterdamse School)は、合理性や普遍性を重視したデ・スティル(蘭: De Stijl)とは異なり、芸術家個人の直観的発想を表現することに重きを置いた。したがって、建築家らは煉瓦壁や瓦屋根などのモチーフを棄却することなしに伝統的な様式から離脱することを目指して、様々な表現に挑んだ。では、オランダの建築家らは、表現のボキャブラリーとして瓦にどのような可能性を見出していたのだろう。それについては次稿以降に譲ることとする。
参考文献
1.
安藤正雄, 深尾精一, 大野和子: 日本桟瓦構法の成立過程におけるオランダ瓦の影響, 住総研, 住総研 研究年報, No.27, pp.285-296, 2007
2.
Petra van Diemen, Niko Koers: A WORK OF ART IN BRICK, Museum Het Schip, 2018




_1-1.jpg)