砂の波に乗るように(小南弘季/東京大学生産技術研究所)

赤く艶のある見た目で知られる石州瓦。山陰を訪れたことのある人であれば、山の裾野に赤い瓦屋根が連なる風景をきっと見たことがあるはず。今回訪ねたのは、島根県は松江市の日本海に面する小さな漁師まち「古浦(こうら)」である。期待通り、赤と黒の甍の波が海岸線に沿って伸びていたが、どうやら少し様子がおかしい。その波は海岸線とは異なる方向に大きくうねっていたのだ。
赤と黒の波
古浦は、島根は松江市街の北西部に位置し、日本海に西面する、その名の通り古代より知られた港のまちである。松江市街までの交通路が整備されており、自動車で20分とその距離は近い。宍道湖北側の集落よりトンネルを抜けると、海岸沿いに広がる赤と黒の瓦屋根が雲の隙間から射し込む陽光を反射して、きらきらと輝く情景が目に入ってくる。
冬の寒さが厳しく積雪量の多い日本海沿岸地区では、吸水しにくく冷害ならびに塩害に強い石州瓦が生産されてきた。石州でとれる粘土が同じく日本三大瓦の三州瓦や淡路瓦よりも高い1,200度以上で焼くことができることによる。これらは焼成時に塗布される釉薬によって光を良く反射する赤褐色の瓦となる。また、鉄砂色と呼ばれる真っ黒の石州瓦も多く生産されている。
古浦を訪れたのは大気が不安定で天気の移り変わりが激しい日であった。11月にもかかわらず、すでに雪が降る寒さであり、海から吹き付ける風が非常に強かったことを思い出す。波は強く、浜辺には砂と潮のしぶきが吹き荒れていた。荒々しい砂浜に雲の隙間より光が差し込む、神在月の美しい風景であった。
海岸沿いの道路より幾分と高い位置に集落が位置していることから、この道路があとから整備されたことが読み取れる。現在、道路の先は建設中であり、行き止まりとなっていた。集落内に入っていくと、小刻みに上下する複雑な地形に沿うようにして土地が割られていることに気がつく。ここは砂丘の上につくられたまちである。

いにしえの浦
古浦はその名の通り、古代より名をもつ浦であった。その浜は伝承において伊弉諾浜と称され、神在月には沖に竜があがると伝えられてきた。また、内陸部に出雲国二ノ宮である佐太神社が鎮座していることからも、古い時代よりこの浦が重要な場所であったことが想像できる。砂丘の一部からは弥生時代の遺跡が発見されている。多くの朝鮮半島からの渡来民がこの浜辺にたどり着いたのであろう。
時代は下って、明徳2年(1391)に製塩業が始まると、それ以降、古浦の塩は御用塩として藩に上納されるようになり、享保年間(1716-36)には砂浜一帯が塩づくりに利用されるようになった。ほかにも大引網漁や造林などが産業とされていたが、住民の8割が製塩業に携わっていたことが当時の記録からわかっている。
しかし、天明7年(1787)に浦の中央を流れる佐田川が整備され、宍道湖とのあいだに運河が開通したことにより、川から滲み出す真水によって製塩を続けることができなくなってしまった。
一方で、運河の開通は古浦を松江藩の外港として発展せしめた。同時にここでの海獲物も干海老や塩鯖、干鮑、煎海鼠などに加工されて出荷されるようになったのである。また、幕末には沿岸警備のために御台場と硝煙本庫が設けられている。古浦は藩と外界をつなぐ窓として機能してきたといえるだろう。
近代以降も運河の利用は続いたが、陸運の発達によって現在は漁港の機能をもつのみとなった。中学高校や病院をもたず、小さな商店と食堂を除いてスーパーやコンビニもない。漁業関係者以外のほとんどの住民は松江市街に通勤していると聞いた。
また、現在のこのまちにおいて語るべきものの1つに島根原子力発電所が挙げられる。この発電所は北部の山の反対側に建設されているため、日常生活においてその存在を目にすることはないものの、野球場や総合体育館、運動公園や文化ホールなどの公共施設や、2020年に完成した宍道湖との間をつなぐトンネル、あるいは現在工事中の海岸通りなどといった過剰に整備されたインフラとして日常の風景に溶け込んでいる。
古浦は、その地理的条件によって、何世代にも渡って公権力に利用され、公共的な投資を受けてきた特殊な場所でもあるのだ。
-1024x839.jpg)
砂丘がつなぐ複数の集落
このまちでは多くのインフラ整備が行われてきたが、現在の空間構造の多くが近代以前においてこの地域の特殊な地形条件の元で形成されたものを継承している。古浦は浜から1キロメートル弱に渡っていくつもの細長い砂丘が連続する複雑な地形を有しており、それらの複数の砂丘に寄り添うように複数の集落が発達してきた。そして戦後には人口の増加や産業構造と世帯構造の変化に伴い、道路沿いの農地や砂丘の上が宅地化され、それらの集落をつなぐようにして居住地が進展していった。
なかでも最も古い集落が浜に面した砂丘上の地域である。この集落では、地面の上下が激しい砂丘の中でも比較的平坦な土地につくられた直線状の通りを軸に、等高線沿いの道とそれに交差する坂道が通され、それらに従って土地が分割されている。そして最も標高の高い場所、つまりは砂丘の頂上にそれぞれ神社と2か所の墓地(現在は移転)が設けられている。密実な土地利用が行われているが、広い庭を敷地の南面にもつ上述の直線状の通りのほかにも、住居と敷地の隙間や高低差を活かして小さいながらも庭を設けている家が多く見られる。
上記の集落から延びる道に沿って内陸の方へ歩いていくと、次第に左右の土地がせりあがっていくことから、砂丘の谷を通っていることがわかる。道に沿って生垣や住居が面しているが、一方でその奥に広がる斜面地は畑や墓地として利用されている。
海禅寺のあたりから傾斜が強くなるが、この寺院は佐陀川の南に東西に横たわる大きな3つの砂丘の西端に位置しており、生い茂る樹々を横目に道は砂丘を上っていく。砂丘の頂上には1980年代につくられた住居が建ち並んでいるが、それらを過ぎ坂を下っていくと、上記の巨大な砂丘の裾野を縁取るように緩やかに広がる集落が現れる。
この集落は浜辺の集落とは異なり、1つ1つの敷地が広く、大きな屋敷と庭を有している。道に沿い住居は展開しているが、各住居の南面の庭が連続し、背後を斜面地上に生い茂る樹木によって囲まれることで、独特な風景がつくり出されている。
砂丘上のおよそ半分はかつての造林の名残りである樹木に覆われているが、それら以外は畑や墓地、あるいは茅場として利用されている。今やその多くは下草の生える空地となっているが、なかにはそれらの荒涼とした風景を借景するように庭を構えている家も見られた。また、砂丘上には道路が通されており、尾根沿いに港側へ通り抜けることができるようになっている。

砂丘から砂丘へ
これまでにも述べてきたように、砂丘の小さなアップダウンの繰り返しが古浦の独特な風景を生み出している。たかだか1キロメートル四方の中で何度丘を上り下りしたことだろうか。小さな坂を下る時には瓦屋根の連なりを見下ろし、ゆったりと上っていく坂を目の前にする時にはその連なりを正面から捉える。そのように屋根の勾配と砂丘の傾きが人間の歩く動作と視覚に同調することによって、古浦の風景の中における石州瓦の存在が強調されるのである。
また、丘の頂上まで上ると突然視界が開け、隣りや少し遠くの砂丘上の住居を望むことができることがある。砂丘の形状をなぞるようにして微妙に上下する瓦屋根はまるで大地の鱗のようである。しかしながら、もっとも興味深いのはこのような風景が道を歩くなかで何度も繰り返し現れることだろう。この小さなまちの中で私たちは複数の集落を渡り歩き、その中に入り込んだり、外から眺めたりすることができるのだ。

運河の町
他方で、古浦のなかで最も低い場所に位置しているのが佐陀川の河口につくられた港町である。この町はほかの集落とは異なり、運河に直行するように複数の道が平行に設けられ、それらに沿った均質的な敷地割りがなされている。運河と海岸から離れるにつれて地面の高さが上がっていくことも興味深い。
運河と海岸に接するこの町では漁業と商売が行われてきたため、運河に面するまちの北端には現在でも商店が残っており、町の内部においても家屋敷と小屋が隣接して配置されている家が多くみられる(現在、小屋の多くが取り壊されつつある)。また、意匠を凝らした住居が多く、古浦が交易港として繫栄していた頃の盛況ぶりを物語っている。
なかでも、最も海際に位置する網元屋敷は、その下に住居機能と小屋を納める極めて巨大な屋根を有する特筆すべき建築であった。赤瓦と黒瓦が交互に葺かれた巨大な瓦屋根と来待石でつくられた棟石がこの建築の重要性を明らかにしている。
運河に沿って並んでいる漁船にはいくつもの大きなランプが据え付けられている。これは夜にイカをおびき寄せるための漁火であり、漁港にはさらに大きなイカ釣り漁船が停泊している。河口より少し遡った先において運河は大きく蛇行する。左岸に砂丘が迫るこの辺りはほかの場所と切り離された穏やかな時間が流れている。かつては多くの船が往来するにぎやかな運河であったことを忘れたかのように、樹々の緑に囲まれた水面の上を白鳥の群れが静かに泳いでいた。

製塩場跡の住宅街
この港町の背部は砂丘の端に位置しており、通りの一部は砂丘の上へと続いていく。運河から浜沿いの集落にかけては複数の砂丘が横たわっており、それらの上にも道路が通され、住居が建ち並んでいる。しかしながら、その半分ほどの土地は畑として利用されているか、荒地や空地となっている。
海に近いが標高は高く真水が浸潤しづらいこの辺り一帯は、かつて製塩場として利用されていたのであった。製塩業が廃止されたあとも空地の状態が続き、1962年の航空写真にはその多くの範囲が貯木場として利用されている様子が記録されている。
1970年代後半までには、現在と同程度の住居が建ち並ぶようになり、住宅街らしさが出てきていたものの、以後それ以上に住宅が建て増しされることはなく、空地が多く残る場所となった。同じ頃につくられた他所の住宅街と同様に、1つ1つの敷地はそれほど大きくなく、住居が余裕なく建てられているが、空地と砂丘の傾斜によって十分な日照と眺望を享受することのできる快適な居住密度が実現されている。
多くの住居はこの辺りの開発が進んでいった当時のものであり、いずれの住居も赤か黒どちらかの色の石州瓦を屋根に葺いている。空地を通して眺めることのできる下草や庭木、そして遠方の山林のなかに赤と黒の屋根が散らばる情景が、時代の波に乗りながら様々に変化し続けてきた海辺のまちにおける現在の生活の平穏さを象徴している。こうした風景こそ、古浦のようなまちが有する普遍的な可能性であるといえるだろう。
小南 弘季(こみなみ・ひろき)
1991年兵庫県生まれ。専門は都市史(日本・近世近代)。東京大学生産技術研究所助教。博士(工学)。小中規模の神社を中心に都市や集落の空間史研究に従事。
現在は低密度居住地域の風景の研究を通してディスクリートな社会の構想を試みている。また、近現代ブラジルにおける文化と建築に関する研究グループを立ち上げ、オルターモダンな建築のありようを指し示すべく活動中。





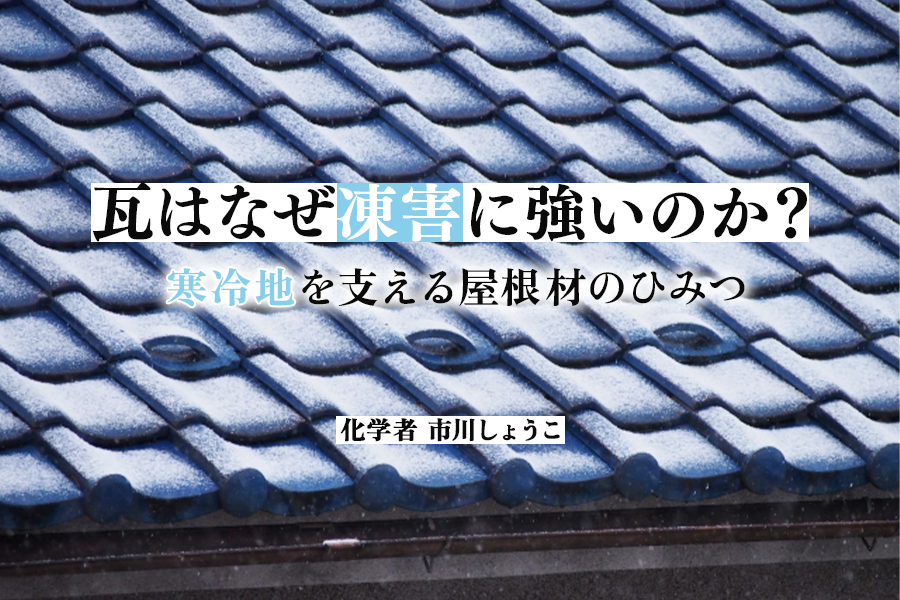



_1-1.jpg)
