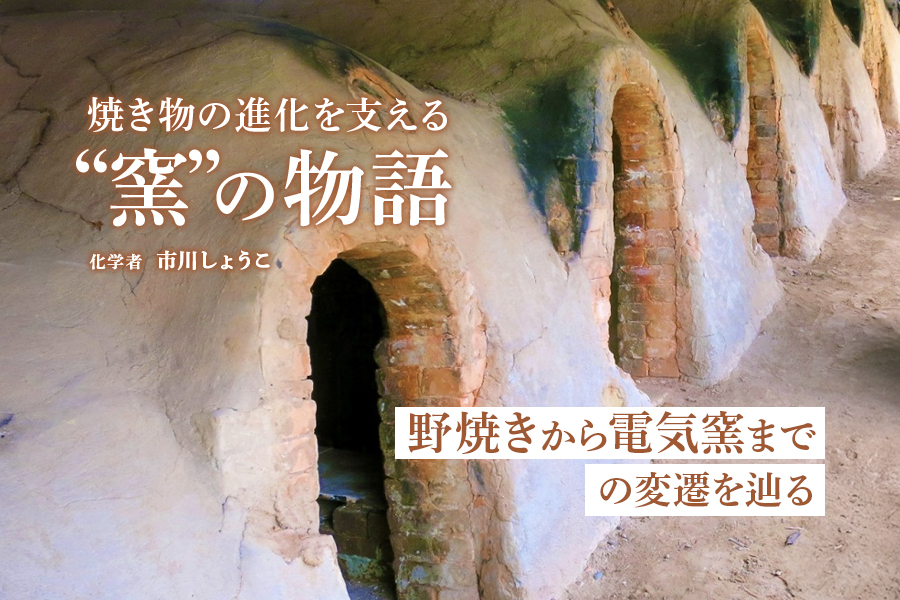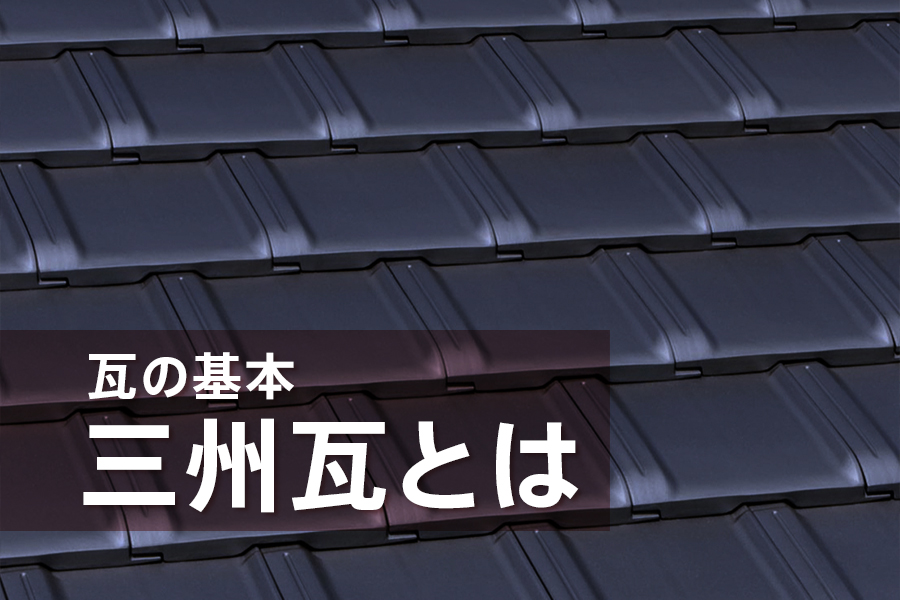陶板はこれからの日本の風景を作る本物の素材(田代彩子/建築家)

私は『「陶板」の過去と現在』という記事の冒頭で、素材を知るにはまずは質感からと述べていた。今回紹介したいのは瓦メーカー鶴弥が開発した新建材で、瓦と同じ陶器からできた壁材「スーパートライWall」。その質感から素材を観察し、深堀りしていきたいと思う。
まず上記の「スーパートライWall」のサンプルを見てもらいたい。タイルや、窯業系サイディングなどの外壁材に似ているため、これが瓦と同じ陶器からできた外壁材とは表面を一見しただけではわからない。つるつるしていなくて、ざらざらしている印象だ。
次に、側面と裏面を捉えた上記の写真を見てもらいたい。側面には、よく見ると赤茶色の部分が顔を出していて、この素材が陶器であるのだと気付く。裏面を見ると、これはもう陶器の表情をしている。一方で、側面に見える空洞の穴。これは陶器でできた瓦の側面とは違うようだ。実際に手にとってみると、タイルや窯業系サイディングとは違いずしっと重く頑丈で丈夫そうだ。瓦よりは重くない。空洞によって軽量化されているのだ。
最後に表面を触って質感を確認してみる。スーパートライWallの壁材ラインナップ「プレーン」「プレーン無垢」「プレーン水面」「プレーン宇宙」の順に紹介していく。いずれも素地は同じで、釉薬の種類やかけ方によって、表面の表情や質感に違いが生まれるのだという。
「プレーン」
小さいつぶのようなものから、ざらざらした印象を感じる。珪砂と呼ばれる砂つぶのようなものが釉薬の中に含まれるため、このような質感になるという。
「プレーン無垢」
焼き物ならではの独特の風合いをそのままに生かした陶板だ。そのため、釉薬もかかっていない。鉄分の多い粘土100%で、焼くと赤色に発色(かえで)し、酸素の少ない中で焼く還元焼成でグレーに発色する(いぶし銀)。余談ではあるが、先ほどの陶板の側面に見える空洞の中は、必然的に酸素が回りづらくなるため、還元焼成のような現象が起き、グレーに発色するのだという。プレーン無垢は無釉タイプで透水試験の結果若干の透水を認めたが、24時間以上では変化がなかった。施釉タイプの他の物は透水がまったく認められなかったため、吸水による膨張も起きなければ、凍害の心配も無い。
「プレーン水面」
水墨のような風合いの陶板。このむら感はどのようにしたらできるのだろうかと疑問に思った。素地は共通して同じということになると、釉薬に秘密があるのだろう。釉薬の種類とかけ方により、焼き上がったときに色むらが出来るのだという。釉薬をかけた時点では色むらはなく、焼き上がると色むらが現れるというのは不思議だ。130年余り瓦を作り続けてきた鶴弥の知識や技術力の結集である。
「プレーン宇宙」
陶板の表面に無数の凹凸があり、星の瞬きのような輝きを放っているのが魅力だ。珪砂の砂つぶとは違い、こちらの凹凸も釉薬の種類によって、盛り上がって焼きあがるとのこと。ここまで述べると、外壁材というより、芸術的な陶器の茶碗制作の話のようにも思うだろう。長い歴史を持ち独自の美的文化を培ってきた陶器、日本の原風景を作り家屋を守ってきた屋根瓦、両者の美点を兼ね備えさらにアップデートしているのが、この陶板壁材だと感じた。
釉薬は質感や表情の違いを作るためだけでなく、色落ちや劣化を起こりにくくし、高耐久にするという利点もある。またつるつると光沢のある釉薬と、ざらざらとした艶消しの釉薬との違いは、ガラス質の成分の違いにある。瓦の持つ驚きの耐久性をそのままに、美しさが30年以上持続する強さ。一般的なサイディングと違い、塗り替えコストが不要で、外壁材の継ぎ目に施すシーリングの劣化によるメンテナンスコストを削減するべくシールレス工法で外壁を施工することができる。
※シールレス工法は通気金具工法のみ対応、出隅・入隅部、開口部は非対応。
ここまで材料そのものを見てきたが、次は張り方や活用方法を見ていきたい。スーパートライWallの張り方は横貼りで、よろい張りもできる。屋外でも屋内でも使用でき、屋内で使用する場合はたて張り対応も可能だ。一枚の横幅1,810mm、高さ324mm。木造軸組30分防火構造、45分準耐火構造、鉄骨造1時間耐火構造の外壁とすることができる。瓦から「スーパートライWall」陶板が生まれた一方で、陶板から陶板屋根材「スーパートライ美軽」という屋根材も開発された。
冒頭でも述べたように、一見瓦と同じようにできている壁材だと気付きにくいが、瓦から派生した壁材だと一眼でわかるようなコンセプチュアルなデザインがあってもいいのではないか。陶板壁材のサイズは横幅1,810mm高さ324mmと大きいが、例えば、瓦と同じサイズ300角ほどにし、よろい張りに張ることで瓦の敷き方を連想させる。外壁に凹凸や陰影ができ、表情のあるものになりそうだ。陶板自体にも強度はあるが、万が一にも割れた際、瓦屋根と同じように一部だけの取り替えで直せそうだ。またよろい張りよりもっと傾斜角度を付けて固定または、角度を自在に扱えるようにし、陶板でルーバーも作れたら良いのではと思う。陶板と太陽光との調和を想像してみた。
長い歴史がある瓦から派生した陶板壁材を深堀してみて、ふと築200年の歴史がある古民家の我が家についても思うことがある。緑豊かな500坪の敷地、現在では入手困難であろう大きな梁や柱、漆喰壁、黒竹の天井、幅広い無垢の床材、いろり、和ダンス、縁側。それらが代々壊されることなく、古民家とその周辺環境を残し守ってきて下さってきた先代の方々のお陰で今の私たちの住まいの豊さがあると思っている。私たちがここに住まう際、既存の大事な部分は残し、現代の生活にもマッチするよう少しだけ現代的な要素をプラスさせていただいた。移り住んで丸3年経つなかで、私たちは未来の世代に何を残せるのか?残していくべきなのかということを、建築も、建築を構成する素材についても考えていかなければならないのではないかと思う。
最後に、瓦は日本の美しい原風景や、誇れる街並みを作ってきた。瓦同様に土からできた陶板は、洋風、レンガ風などのフェイクでなく、土本来の素材でできた本物の素材である。またスーパートライWall陶板は数種類の粘土に、瓦のリサイクル品でもあるシャモットをブレンドして作られていることもあり、持続可能な素材でもある。平板瓦と漆喰で構成される「なまこ壁」が伝統的な位置付で今もなお大切にされているように、スーパートライWallも日本の街並みの美しさに付与し、新たな伝統様式や歴史を作っていく可能性を感じた。