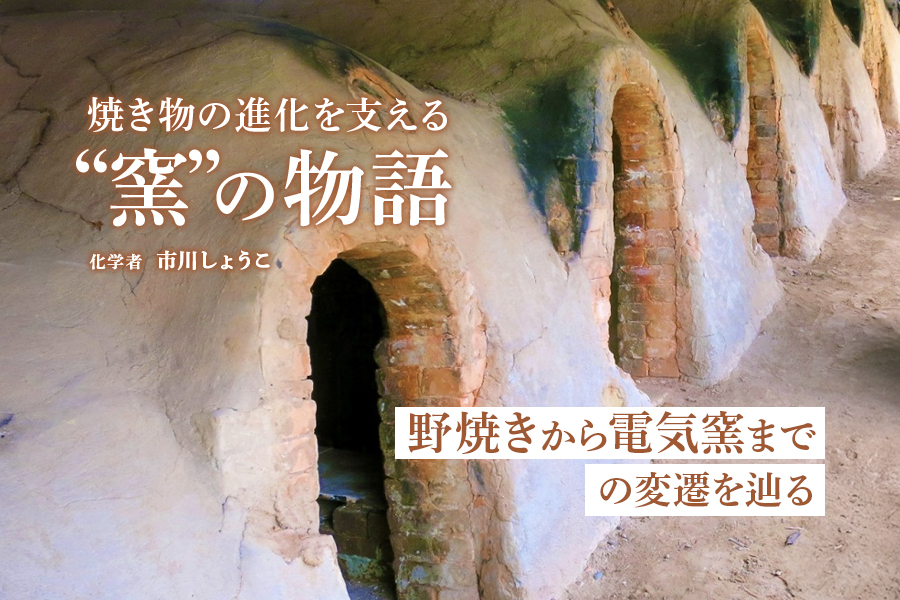瓦屋根を修理する時の注意点とは?費用相場や補助金も紹介

瓦は耐久性に優れた屋根材です。
日本に瓦が伝来したのは西暦588年ごろと言われていますが、当時に造られた瓦が1400年以上経った今でも現役で残っています。
現在の粘土瓦でも耐用年数は約60年あり、高い耐久性は特徴の1つです。
しかし、瓦が傷まなくても下地が傷むため、瓦屋根でも雨漏りのトラブルが起きる場合があります。
雨漏りのトラブルが起きると、どうしたらいいのか分からずに慌てる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、トラブル時にも適切な判断が行えるよう、瓦屋根を修理する時の注意点3つと、具体的な修理方法、修理方法別の費用相場について取り上げます。
最後に、補助金の情報もご紹介しますので参考にしていただけると幸いです。
(このメディアを運営する瓦メーカーの株式会社 鶴弥では、2023年より「粘土瓦60年保証」を開始しています。)
瓦屋根を修理する時の注意点3つ

「修理業者に頼むと高くなりそうだから」と自分で修理しようとしたり、安易に業者を選ぶのは得策ではありません。
瓦屋根を修理する時には、以下3つの注意点を頭に置いておきましょう。
①:自分で修理するのはリスクがある(DIY)
②:訪問販売業者の指摘をうのみにしない
③:修理の期間と時期に気をつける
それぞれ解説します。
①:自分で修理するのはリスクがある(DIY)
1つ目、自分で修理するのはリスクがあることを念頭におきましょう。
瓦屋根が割れた場合の修理方法として、防水テープで補修したり、パテで補強する方法があります。
修理に必要な防水テープやパテは、ホームセンターやネットショップで手に入れることができるため、自分で瓦を修理しようと考える方もいるのではないでしょうか。
しかし、瓦屋根の修理は足場の悪い高所作業になり、転落する危険があります。
また、慣れない屋根の上での作業により、瓦を破損するケースがあります。
さらに、瓦の固定が甘いことで定位置からずれてしまい、雨水が内部に浸入して雨漏りにつながる可能性もあります。
瓦屋根が破損して交換が必要な場合や、雨漏りの修理は、業者に依頼するのが良いでしょう。
②:訪問販売業者の指摘をうのみにしない
2つ目、訪問販売業者の指摘をうのみにしないようにしましょう。
全ての訪問販売業者がトラブルの原因になるわけではありませんが、悪質な訪問販売業者が存在しているのは事実です。
例えば、屋根の点検を無料で行うと訪問し、虚偽の報告を行って高額な屋根修理契約を結ばせるケースがあります。
点検時の屋根の状態を写真で見せてもらったとしても、あらかじめ用意しておいた偽の写真を使って報告するような手口もあるため、訪問販売業者の指摘には注意が必要です。
対策として、その場で屋根には登らせずに、名刺などから会社の所在地や地域の工事実績をチェックする方法があります。
また、契約を結んだ場合は、クーリングオフ期間が8日間あるため、早めの契約解除を検討しましょう。
屋根の修理は、地域密着型の信頼できる業者に任せると安心です。
③:修理の期間と時期に気をつける
3つ目、修理の期間と時期に気をつけましょう。
例えば、雨漏りに気づいて早急に修理をしたい場合でも、着工まで1か月程度かかることがあります。
雨漏りが酷くなってから修理を検討した場合、雨漏りのする室内で長く過ごさなければなりません。
雨漏りが酷くない段階で業者を探して見積もり内容を検討し、着工から施工完了までの期間を想定しておくことが大切です。
また、屋根の修理は季節に関係なく行うことができますが、春と秋は依頼が増える時期です。
そのため、希望日に施工できず、1〜2か月程度待つ場合もあります。修理の時期は余裕を持って検討すると良いでしょう。
さらに、梅雨の時期は屋根の修理ができず、工期の予定が伸びる可能性があります。
修理に適したタイミングは、梅雨が始まる前と、気温が落ち着いて晴れる日が多い9月下旬〜11月初旬ごろがベストです。
瓦屋根の修理をする時の注意点を把握したところで、具体的にどのような修理方法があるのか、解説しましょう。
瓦屋根を修理するための3つの方法

瓦屋根を修理するための方法は、以下の3つです。
①部分修理
②葺き直し
③葺き替え
それぞれ解説します。
①:部分修理
部分修理は、狭い範囲での劣化や損傷に合わせた修理方法です。
例えば、漆くいの剥がれや崩れがある場合は、既存の漆くいを取り除いて新しく施工し直します。
雨水が溜まってしまったり、施工不良の可能性がある場合は修理が必要な瓦を交換します。
狭い範囲という条件はありますが、部分修理はコストを抑えられるのがメリットです。
②:葺き直し
葺き直しは、下地部分を修理して、既存の瓦を葺き直す修理方法です。
瓦の耐用年数は下地部分より長いため、下地部分の補修や交換をして屋根瓦を再利用します。
また、下地部分に広く異常があり、瓦には問題がなければ、瓦の購入費用を抑えられるメリットがあります。
葺き直しは一般的によく行われる修理方法の1つですが、既存の瓦を使用するため修理後の屋根の見た目は変わりません。
ここでの注意点としては、古い瓦には防災フックがついていない(防災瓦ではない)可能性がありますので、地震、台風での対策には充分ではありません。防災フックの有無を確認の上で、葺き直しで良いのか検討するのが良いでしょう。
修理の機会に屋根材を変えたい時は、次に紹介する葺き替えが良いでしょう。
③:葺き替え
葺き替えは、既存の瓦全体を取り除いて新しい屋根材を設置する修理方法です。
雨漏りが複数箇所で発生して、屋根全体に広い範囲で修理が必要な場合や、新しい屋根材で外観を美しくしたい場合に最適です。
また、屋根瓦だけでなく、下地部分を一緒に修理するケースもあります。
下地の修理も行えば、屋根の耐久性が全体的に良くなります。
しかし、修理方法の中では最も高額になることが多いため、予算に合わせて検討するようにしましょう。
では、瓦屋根の修理を業者に依頼する場合、費用はどのくらいかかるのでしょうか。
修理方法別の費用相場

次に、費用相場について解説します。
費用相場は、修理方法によって異なります。
瓦屋根の修理方法は、主に3つあります。
①:部分修理
②:葺き直し
③:葺き替え
それぞれ解説します。
①:部分修理
部分修理は、狭い範囲での劣化や損傷を補修する修理方法です。
例えば、瓦のズレを正しく補修する場合は5万円程度が相場です。
瓦にヒビや割れがある場合は、瓦の交換費用として1枚あたり1万〜3万円程度が相場です。
瓦の種類や枚数、下地調整の有無などによってトータルの修理費用が変わります。
また、棟瓦にズレやゆがみがあり、棟の取り直しをする場合は1mあたり1万〜3万円程度が相場です。
漆喰の割れや剥がれなどがあると、既存の漆喰を剥がして詰め直す修理が行われます。
この場合は、1mあたり4000〜6000円程度が相場です。
②:葺き直し
葺き直しは、一般的な30坪の戸建て住宅の場合で、下地調整や足場費用などを含めると80万〜200万円程度が相場です。
葺き直しの修理は既存の瓦を撤去して、その下にある防水紙や野地板を交換した後に瓦を戻します。
雨漏りが発生していたり、とくにメンテナンスをしていない築30年以上の住宅は、最も費用がかかるでしょう。
また、下地の野地板に劣化が見られない場合は、野地板を交換しない葺き直しで費用を抑えることが可能です。
さらに、塗り直しが必要な屋根材は葺き直し費用に加えて塗装費用がかかるため、後述の葺き替えと価格差が少なくなる傾向にあります。
その点、粘土瓦は塗り直しが必要ないため、コストパフォーマンスが良くなります。
③:葺き替え
葺き替えは、一般的な30坪の戸建て住宅の場合で、下地調整や足場費用などを含めると140万〜250万円程度が相場です。
葺き替えは、既存の屋根材や屋根の形状などにより費用が変わりますが、新しい屋根材を用いるため、葺き直しよりもコストがかかります。
また、屋根の修理を機会に、太陽光パネルの設置を検討するケースも少なくありません。
太陽光パネルは、設置容量によって単価が変わります。
1kWあたり26万円が相場で、一般的な4〜5kWの容量の場合は104万〜130万円程度になります。
さらに、1kWあたり7万円程度の工事費が加わりますが、設置後に定期点検や清掃費用が必要です。
屋根の葺き替えにかかる期間や費用の内訳などは、こちらの記事をご参照ください。
瓦の葺き替えはいつ必要?瓦の特性・葺き替えの重要性とポイントを解説
以上のように、瓦屋根の葺き直しや葺き替えの場合は高額になりがちです。
各地の市区町村ではさまざまな補助制度がありますが、瓦屋根の修理に活用できる補助金はないのでしょうか。
瓦屋根の修理に活用できる補助金

最後に、瓦屋根の修理に活用できる補助金をご紹介します。
①:住宅・建築物安全ストック形成事業
②:長期優良住宅化リフォーム推進事業
③:地方自治体独自の補助金
それぞれ解説します。
①:住宅・建築物安全ストック形成事業
瓦屋根の耐風診断や、瓦屋根の脱落を防ぐために改修工事を行う場合に、申請することができます。
耐風診断は、瓦屋根の緊結方法が建築基準法に適合しているか、かわらぶき技能士や瓦屋根工事技士などに診断してもらうケースです。
診断費用の3分の2で、最大2.1万円が補助額になります。
また、改修工事とは、建築基準法に適合しない瓦屋根を、所定の耐風性能を有する屋根に葺き替え工事をする場合です。
工事費用の23%で、最大55.2万円が補助額になります。
対象は基準風速32m/s以上の区域か、地域防災計画等で地方公共団体が指定する区域です。
概要はこちらのHPをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000146.html
②:長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、良質な住宅の保全や性能向上を目的としたリフォーム、子育て世帯向け改修などに対する補助事業です。
補助を受けるためには、建物診断(インスペクション)を実施して、維持保全計画と履歴を作成する必要があります。
また、工事後に耐震性と劣化対策、省エネルギー性が確保されているという条件もあります。
補助対象になるのは工事費とインスペクションなどの作成費で、補助率は費用の3分の1です。
限度額は、1戸あたり原則100万円となっています。
具体的に対象となる屋根工事には、瓦屋根の耐風・耐震工事や屋根の補修・軽量化、金物の補強や足場の設置などがあります。
事業者登録前に締結した工事請負契約や、住宅登録前に着手したリフォーム事業などは、
補助の対象外になりますので、注意が必要です。
概要はこちらのHPをご参照ください。
https://www.kenken.go.jp/chouki_r/
③:地方自治体独自の補助金
地方自治体で、独自の補助金制度を用意しているケースがあります。
屋根修理の負担額を減らすために、各自治体のHPを確認しておくと良いでしょう。
以上、瓦屋根の修理に活用できる補助金についてのご紹介でした。
なお、一般的に補助金を申請する際には、次のような条件があります。
・工事前の申請が必要
・申請時に見積書が必要
・募集人数や申請金額の制限
条件には注意して補助金を活用することが大切です。
劣化状態の確認と修理は専門の業者に頼むと安心

瓦屋根を修理する時の注意点3つと、修理方法別の費用相場をご紹介しました。
修理方法別の費用相場を理解しておけば、高額な屋根修理の契約を事前に防ぐことができます。
また、自分で修理を試みることで瓦を破損させてしまった場合や瓦が定位置からずれて雨漏りを引き起こしてしまった場合などは、結果的に修理費用が高くなってしまいます。
安全かつ適切な費用で修理するために、取り上げた注意点は確認しておくと良いでしょう。
弊社、株式会社鶴弥は明治20年創業の粘土瓦メーカーです。
登録施工店のご紹介も可能ですので、以下の施工事例ページを参考の上、ぜひご相談ください。