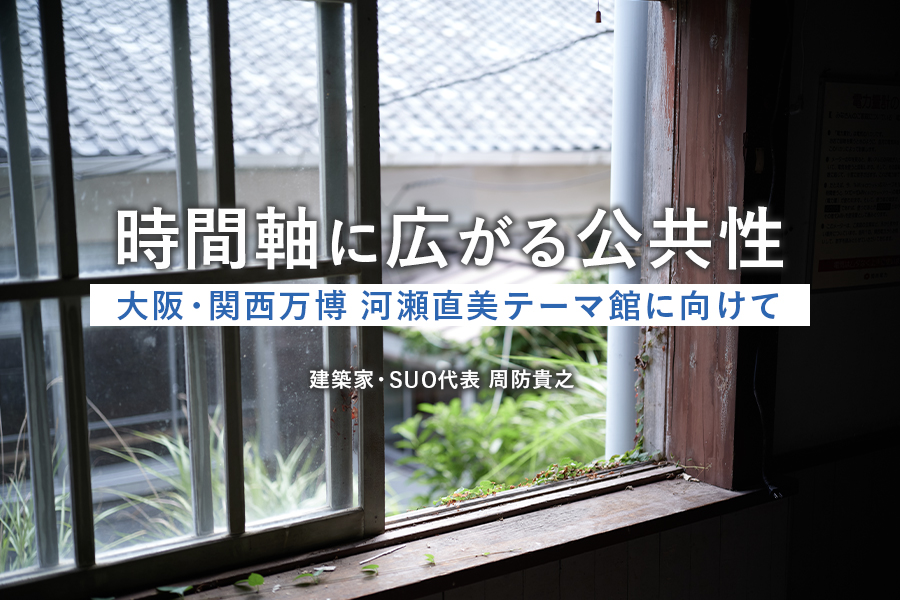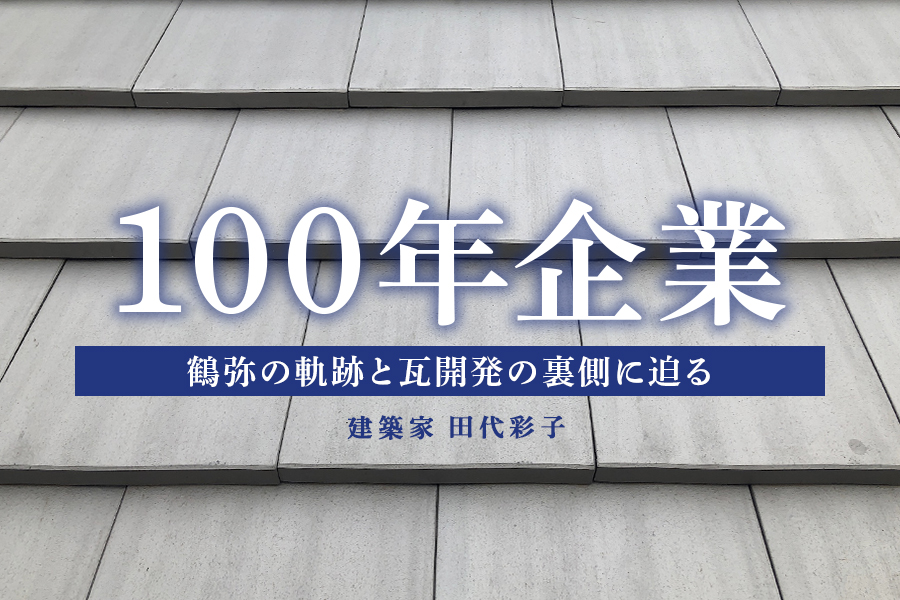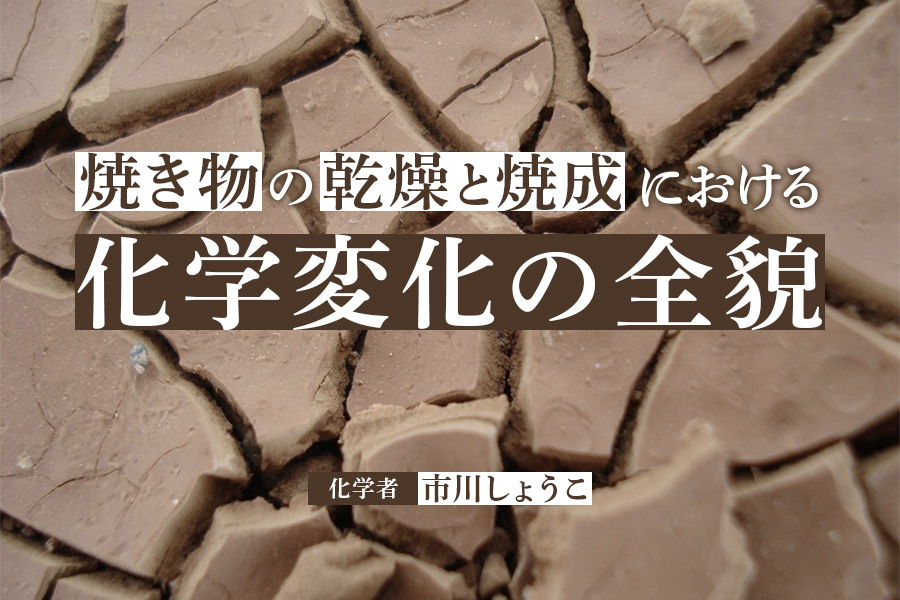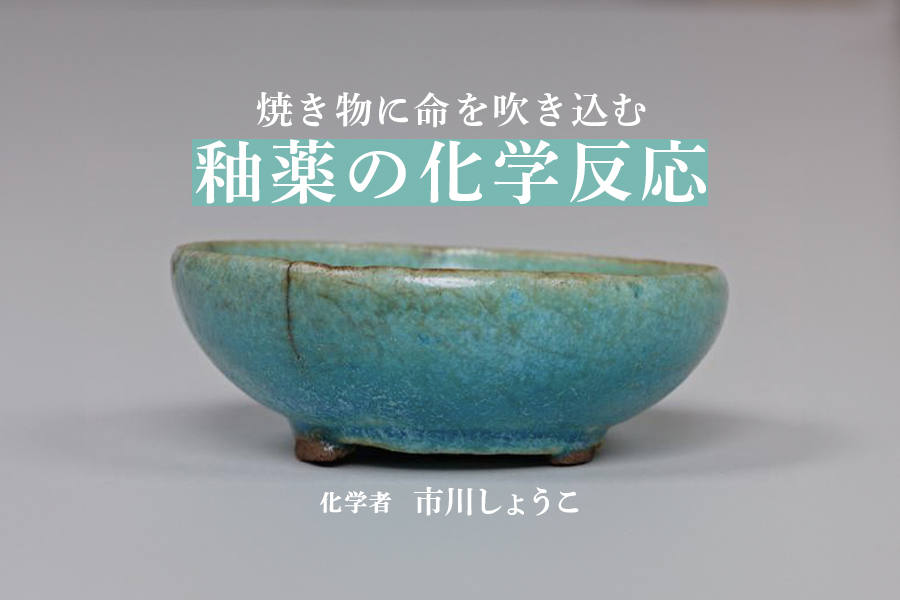アルド・ロッシの家形/家型(イエガタ) 単家族住居における材料と形式(片桐 悠自/組積研スタジオ、東京都市大学)

丘からふいた一陣の風、庭の木々の花々のように、ベランダに響く雨音のように、ふと意識されたとき、建築に生命が見出される気がする。
つい先日(2025年3月)、単家族住居をはじめとするアルド・ロッシ(1931-1997)の建築を再訪する機会があった。彼の建築は、社会的生産と不可分な「類型」に基づいて建てられ、それ故に、ひとつの「時間-環境」を構築する、風景の一部となる。
単なる形式や作品を超えた都市の外形として、日常のなかに僅かな違和感を差し込んだ建築。本稿では、ロッシが1970年代に手掛けた「単家族住居 case unifamiliari」と呼ばれる住宅群を中心に、彼の家形/家型のもつ材料と形式の特徴をとりあげる。そのどれもが、普通の民家でみかけるような、材料と構法で建設されているのだが、ロッシの見慣れた住宅を異化するような、造景の作用があるようにみえる。筆者が撮った写真と見比べながら、北イタリアの風と霧と土に根ざした感覚の背後にある、表象を追ってみたい。
空の青みと、光と風
空色に映える青。ロッシは、天候がもたらす金属屋根の微妙な変化に関心を抱いており、それは、1970年代の四〇歳を過ぎたあたりから、積極的に建築へと取り入れられた。元学生であり協働者のジャンニ・ブラギエーリと設計した「モデナのサン・カタルド墓地拡張計画」(1971-84年頃)については、敷地境界の東西南をコの字で区切る長大な納骨堂が(一部未完のままで)実現したが、この屋根は、明るい空色のシートメタルが葺かれた。この屋根の色について、『アルド・ロッシ自伝』(1981)をひくなら、以下のような記述がみられる。
>(中略)シートメタルで覆った巨大な青屋根は昼光や薄光に輝き、また四季折々の光にも反応していかにも繊細であり、今日これを見渡すと青色が深く翳ったり光彩を放ったりする。その壁は古い墓地に用いられたエミリア地方の煉瓦をピンクのスタッコで覆ったもので、光の効果が極端に現れ、ほとんど白色にみえたり赤紫に変化したりする。実際プロジェクトの段階でこの建物はすでにポー川流域の深い霧や、洪水の後何年も打ち捨てられてきた河辺の廃屋とともに存するものだった。
ロッシが回顧するに、エミリア=ロマーニャのポー川流域の、霧深い風景や崩れ落ち打ち捨てられた組積造の建物のイメージが、設計当初から付帯していた。アルプス山脈と、イタリアの背骨であるアペニン山脈の間にあるこの巨大なポー平野は、エミリア・ロマーニャ州のほか、ロッシの育ったロンバルディア州のミラノと似て、じめじめとして一日中霧深いときもあれば、からっと晴れるときもある。空の色は、刻々と変化し、曇り空の灰色から、雲の多い空色、湖と反射される薄暮の色など、風景と一体となっている。
1972年に『コントロスパツィオ』誌上で発表された設計趣旨説明文「空の青み L’Azzurro del Cielo」では、この納骨堂の屋根は白く仕上げられ、壁も灰色の石などで無彩色となることが予定されていた。
ロッシが、数多くの色の使用に踏み切ったのは、「ガララテーゼの集合住宅」の協働者の、カルロ・アイモニーノの影響だろうか。当初、聖所として計画され、のちにエレベーター付きの納骨堂となった計画敷地中央に位置する立方体状の建物も、灰色で想定されていたものが、最終的には赤く塗られた。1984年の東京での講演会では、「このスタッコの色はモデナ市の色で、墓地の周囲はこれからも緑の植物が生い茂ることでしょう」と述べ、赤色と生い茂る草の緑の対比によって、風景を形作ることを意図していた。青い金属ペイントが、ロッシの「大好きな色」を用いたものであり、光の反射とともに、青空と一体化して、淡いピンク色の壁を強調することもある。青い金属ペイントは、墓地を仕切る窓やゲートにも用いられ、曇天模様のなかで、見えない青空を映し出す。
「モデナ墓地」とほぼ同時期に設計された「ファニャーノ・オローナの小学校」(1972-76)にある守衛棟の、黄色いしっくいの壁体、建築家自身によって経年変化することが意図されていた。2025年3月10日に巡検したところ、妻面に雨だれ跡が多く見られ、雑誌発表時の明るいフラットの色彩から多くの時間が経っていることを窺い知ることができた。
筆者撮影、2025年3月

「モデナ墓地」で展開した納骨堂という「死者の家」の家形は、テラスハウスという「生者のための家形」へと置き換えられた。視察の日は、今にも雨が降りそうな(若干、小雨だったかもしれない)、霧模様の曇天の日で、経年を経た黄褐色の壁体に対し、鈍色の金属の屋根が空模様と相まって、家形の屋根が空に溶け込んだようにみえる。
(家形)+(丸窓)↔(家型)
ひとまとまりの家形ヴォリュームに金属材料の屋根を葺くこと、こうした操作は、ポー平原に設計された3つの単家族住居にも見出せる。
ミラノからほど近い北イタリア・ロンバルディア州の街モッツォにある最初の単家族住居は、協働者のブラギエーリほか、設計コレクティブCOPRATとして、ひとつの白い家形のヴォリュームに4戸の住宅が計画されたものが1979年ごろ竣工している。これは、切妻屋根の平入りの建物として、ストライプ状の同形平面をもつ4戸の住宅を1棟のヴォリュームにまとめたものであり、ありふれた白しっくいの壁に、萌葱色の金属ペイント板が葺かれた屋根をもつ。雨樋、ポーチの屋根、外塀、鎧戸など、ペイントされた部分は萌葱の緑で統一されており、異なる色彩の似た材料を用いた形式の反復によって、「モデナ墓地」の納骨堂や「ファニャーノ・オローナの守衛棟」との類似が見出される。
家形ヴォリュームの妻面には丸窓が配され、萌葱色の丸サッシで囲われる。虫除けの網の背後に、十字窓があるのがわかる。中央にちょこんと穿たれた丸窓は、北イタリアにおける蒸し暑い夏を防ぐための換気を兼ねているのであろう。金属板が太陽光の熱を受け止め、小屋裏には熱い空気が充満する。丸窓は溜まった熱気のための隘路である。
熱の隘路たる丸窓は、設備機能の意味から、中央に穿たれるのが自然だ。建築家の意図以上に、生産的な「類型(タイプ)」として受け継がれてきたものである。
「モッツォの単家族住居」は、通常のイタリアの住宅の黄色や赤褐色の土壁をもつ家形を異化するように、白く塗られた。白いしっくいは、若きロッシが、ドイツの建築家オズヴァルト・マティアス・ウンガースの住宅において着目していたように、モダニズム建築から引き継いだ「類型」である。
ここで、近代以降に用いられた白い壁に、ロッシは墓地で適用した金属材料の色彩を、屋根に付加する。
空の色とも異なる緑色の家形ヴォリュームは、周辺の住宅の赤い瓦葺の屋根とは異なるものとして、認識される。白い壁と金属材料のマティエールをもってモダニズム以降の20世紀の建築を参照する。昔懐かしいペディメントを想起させる勾配屋根でありながら、どこか近代的なのだ。ここで「家形house-form」のもつ材料と形式のもつ意味は宙吊りにされ、さりげなく見るものの日常に違和感を挿入する「家型 house-type」となる。
「家形」の形は、丸窓をつけることで、一挙に「おうちらしく」なってしまう。子どもが描く絵でよくみられるように、妻面に穿たれた丸窓は、外形として、「家形」のヴォリュームを、「家型」へと変換する最小の操作のように見える。おそらくは、こうもいえそうだ。
(家形)+(丸窓)↔(家型)
「家形」と「丸窓」は「家型」の平衡状態を作り出す。それは、部分でありながら、全体を示し、全体を示しながらもふたつの部分への弁証法的な分裂状態にある。記憶のなかで、「家形」と「丸窓」は、確固たる形式というよりは、くっついたり離れたりして、「家型」として宙吊りになっている。「型」とは、そんな物質的状態を自ら示すものとなる。
アルベルティと丸窓と光
「家形」のヴォリュームは、風景を異化しながら、「家型」となる。住宅の丸窓は設備的(モダニズムそして、過去の教会建築のような三角形と四角形を合成したペディメントをも想起させる。建築の要素がつくる風景が即物的な意味を超えて、過去の時間を参照する手がかりとなる。こうした丸窓の意味をロッシに教えたようにみえるのが、彼が敬愛するルネッサンス時代の建築家アルベルティだ。
アルベルティ設計の「マントヴァのサンタンドレア教会」(15世紀末着工/18世紀末竣工)も丸窓が用いられたが、サンタンドレア教会内部の丸窓の写真を、ロッシは『自伝』で参照し、強く関心を抱いていたようだ。街路から見えるペディメントの下にある丸窓は、めくら窓になっている。内部に光をもたらす大きな丸窓は、ファサードからセットバックした「大傘」の下にある、もうひとつの丸窓からもたらされる。
「大傘」の下の真の丸窓と、街路側のみせかけの丸窓。本来古典主義のペディメントとともに、用いられていた丸窓は、アルベルティによって、二重のファサードとして翻案される。十分に前面広場の大きさがとれない街路側のファサードに、「看板」としてつくられたペディメントの奥は、「大傘」を介して、ドームを支える。都市マントヴァを示す外形は、ペディメントとドームによって保証される。
さらに、アルベルティの意図した光の効果は、アドリア海に面した街・リミニに位置する「テンピオ・マラテスティアーノ」にも見られる。既存の中世の壁体をすっぽり包みながら、絶妙な距離を保つ「白い船 La nave bianca」だ。付加された白い大理石の壁体と既存壁体のクリアランスには、空の気分を反映しながら、時々刻々と移り変わる影が投射される。
筆者撮影、2024年8月
いまや、教会のペディメントは、民家や公共建築の「家形(イエガタ)」へと変容した。
小規模な住宅建築ならば、明かり取りというより、小屋裏の換気を兼ねた丸窓となる。家形と丸窓は、神殿に用いられた家形の歴史的意味を無化しつつも、ときに想起させ、日常のなかに挿入される。形式は材料へと、材料は形式へと、混ぜ合わされることで建築となることをアルベルティは知っていたのでないか。ロッシが、「サンタンドレア教会」で参照した丸窓もまた、その意味で解釈されるものではないだろうか。
「小さな家形」と「大きな家形」
木々や草花と同じく、建築は、風景のなかで外形として取り込まれ、外形として枠付けられる。日常の認識のなかでふと気がつくときにはじめて、事物の生は認識される。
「モッツォの単家族住居」の場合は、同じような萌葱色のペイントでコーティングされた金属材料によるエントランスポーチが付加されている。このエレメントだけ見ると、本体の家形のヴォリューム以上に、連続したポーチの三角屋根に目が行く。「セグラーテの噴水」(1965-67)に代表されるロッシの「△噴水」を思い起こさせる。
屋根に金属板スレート葺きが使われたのは、エントランスポーチの「小さい家形」と、躰体の「大きな家形」と一体の外形として認識させる試みだったのだろう。同時期にマントヴァ近郊の町に設計された「ゴイトの単家族住居」(1979)は、その試みを伝えてくれる。「大きな家形」のヴォリュームの平入りで敷設された「小さな家形」の屋根が、青色の金属版で葺かれた単家族住居だ。
八棟のテラスハウスが、家形のエントランスポーチを向かい合うかたちで二列に整列する。このうちの七棟は、一棟あたり、左右対称に二戸に分割されている。二家族が住めるようにするため、ヴォリュームに平入りで設けられた「小さな家形」のエントランスポーチの左右からそれぞれ住戸にアクセスする。中庭を見るならば、平入りの「小さな家形」と妻面の「大きな家形」が反復され、奇妙な印象をうける。
八棟のうち、他の七つに比べて半分のヴォリュームをもつ一棟は一戸のみであり、この住戸のみ、個人用の前庭を大きくとられている。この「大きな家形」は、妻入の「さらに小さな家形」のエントランスをもつ。「さらに小さな家形」のエントランスは、妻面に比べてかなり小さく、45度に近い屋根勾配のものだ。
都市の外形の異化
さらに、ロッシの単家族住居の屋根に瓦が用いられた例を紹介したい。「ゴイトの単家族住居」と同時期の「ペゴニャーガの単家族住居」(1979-80)では、黄色い壁体に赤褐色の瓦屋根が用いられた。黄色いしっくいに、瓦屋根というほとんど周辺の住宅と変わらない被覆材で覆われたこの住宅は、庭を挟んで2棟向かい合った細長いテラスハウスであり、自動車置き場を兼ねた長屋門を加えた3棟で構成される。
庭側は雨樋と一体となった柱が並ぶ回廊となっており、高さ6.6m、幅30cmの正方形のコンクリート各柱が並んだ回廊が特徴的だ。中央あたりに位置する1本の柱は2倍正方形断面をもち、その真ん中を雨樋のパイプが伝う。回廊は、幅3mであり、蔦の絡まった角柱と、植木鉢、緑とともに、家形という強い幾何学形式が一旦保留される。MAXXI(イタリア国立21世紀美術館)所蔵図面をみると、屋根勾配は30度で、正三角形を半分にした比例が用いられていた。実際は、図面よりも棟木を下げて、よりゆるやかな勾配屋根が実現している。
「ペゴニャーガの単家族住居」の断面図、MAXXI所蔵図面をもとに筆者作成。現地調査から導出した要素(屋根勾配・丸窓・雨樋・半外部の開口)を赤の実線で記入している。
風景の生、建物の生
ロッシの単家族住居の形式は、“家形”を反復しながら、様々な材料のイメージとともに記憶される。北イタリア地域にありふれた構法で建設され、周囲の環境に溶け込んでいる。しかし建築家によって反復された「家形/家型」に着目するなら、その建築の生命は、日常生活をどこか異化しながら、人間と関わり合っているのでないか。
ロッシは、1971年11月のミラノ工科大学の罷免後、1972年よりETH(スイス連邦工科大学チューリッヒ校)において客員教授として教鞭を執った。ここでジャック・ヘルツォークやピエール・デ・ムロン(ド・ムーロン)などを指導したことはよく知られている。同校ではティチーノ州の民家調査などを行い、アノニマスに成立した土地固有の建築に興味をもったという。たとえば、同校の講義「建築の理論」(1972〜1978年頃)では、風土について以下のような記述がみられる。
>実証的な意味で、いわば、文明生活とそれが現れる社会と不可分な創造物としての建築を考察するならば、建築とは、それ自体集合的な自然としてあるものである。
最初に人間たちがそうしたように、まず住居が建てられたのであり、その最初期の住居において、人々はより望ましい生の環境を実現することを試みた。住居は、微気候ないし人工的な気候を構築しながら、同時に美学的な志向性に基づいて建設される。人々は、建築をひとつの時間として始めたのであり、それらは、都市の最初期の痕跡となっている。つまり、建築とは、文明をそれ自体で形づくる先天的なものである。建築は、永続的で、普遍的でなくてはならないものなのだ。
この文章は、先立って行われたヴェネツィア建築大学(IUAV)での1965-1966年の講義「類型学、マニュアル的なもの、建築(Tipologia, manualistica e architettura)」の部分抜粋であり、ロッシの都市と環境における建築のあり方が表れている。
建物の生のあり方は、人間、動物、木々、風、雲、事物などが混じり合った、その時々の瞬間に、見出される。建築家は、そのたびごとに、造られた内部の微気候を設えるのであるが、それは住まい手や使い手の無意識のイメージへと遡行するような、風当たりだったり、季節の変化だったりする。それこそが、彼自身の講義で開陳され、後の『自伝』で何度も触れられる「時間-環境(tempo テンポ)」なのであろう。
永続的かつ普遍的な「モニュメント」とは、建築が自然の摂理のなかで、内部という微気候を布置することで、風景を作り出す。それは微妙に風景を異化することで、ある瞬間に建物の生命が認識される。それが、ロッシが追求した「家形/家型」なのではないだろうか。
【参考文献・出典】
1 筆者は以前、「ファニャーノ・オローナの小学校」のエントランスポーチにおけるサッシのない窓について論じた。片桐悠自「聖なる侵入 アルド・ロッシの窓(連載 アルド・ロッシの窓)」https://madoken.jp/series/14927/(最終アクセス 2025年3月29日)補足するなら、ロッシ自身の意図として、ガラスのない吹きさらしの窓によって、光を設計当初より取り入れることが意図されていたことが、彼の手記『青のノート』において言及されている。「当初より、エントランスの窓の十字は吹きさらしで考えており[per le grandi croci vuote delle finestre dell’atrio]、これはなによりも、(映画監督カール・テオドア・)ドライヤーの光であると同時に、我々のロンバルディアの湖畔の光とも隔たってないものであり、霧を拡散し、空を世界で一番青くするものである。他の箇所、クーポラのガラスや、自転車置き場の青いポルティコ、パーゴラは、建設中に付け加えられた。」;ROSSI, Aldo, Quaderno Azzurro (24), Electa, 1999. 1979年6月18日の記述。
2アルド・ロッシ『アルド・ロッシ自伝』三宅理一 訳、 鹿島出版会、1984, p.38. 一部原書をもとに改変。ROSSI, Aldo, A Scientific Autobiography, Cambridge; Mass., MIT Press, 1981, p.15
3“La copertura del portico perimetrale (colombari), costituita da un elemento triangolare cavo in cemento, e verniciata dibianco.” ; Rossi, Aldo, ”L’azzurro del cielo”, Controspazio(10), 1972, p.8
4アルド・ロッシ「アルド・ロッシが語る建築と都市 (第25回新建築講演会)」, 『au』(171), 1984, p.26
5片桐悠自『アルド・ロッシ 記憶の幾何学』、鹿島出版会、2024, pp.60-61
6同時代のスペインにおけるロッシの理論的代弁者だったラファエル・モネオ[José Rafael MONEO VALLÉS]は、「モッツォの単家族住居」が、ロッシ、ブラギエーリ、アッティリオ・ピッツィゴーニ[Attilio PIZZIGONI]との設計コレクティブCOPRATによる共同設計であったと指摘する。MONEO,Rafael “L’apparenza come realtà. Considerazioni sull’opera di Aldo Rossi”, Intorno ad aldo rossi e alla sua architettura., Occhipinti, Chiara (ed.), Milan: Politecnico di Milano, 2013., p.41 なお、MAXXI所蔵図面の基本計画の一部には、ピッツィゴーニの名前だけ記されている図面もある。“809: “Unità residenziale a Mozzo: esecutivo architettonico” (1977 9”lug.), https://collezionearchitettura.maxxi.art/patrimonio/5b453830-547e-4bd5-b8f4-4b23f5db404a/809-unita-residenziale-a-mozzo-esecutivo-architettonico-1977-lug(最終アクセス 2025年3月29日)なお同アーカイブが所蔵する「モッツォの単家族住居」に関するロッシのエスキースから判断すると、竣工したものとは大きく異なる陸屋根の案が当初計画されていたようである。
7 ロッシにおける三角噴水の反復と、形式の“平衡状態”がなす物質的な記憶についての以下の拙論も参照。Yuji KATAGIRI, “Repetition of Triangle Fountain of Aldo Rossi: Geometrical Analogy of Architecture”, ICGG 2018 – Proceedings of the 18th International Conference on Geometry and Graphics, 2019, pp 809-819.
8 2024年12月21日におこなわれた「片桐悠自『アルド・ロッシ 記憶の幾何学』書評会』(立命館大学朱雀キャンパス)における岡北一孝氏(アルベルティ研究、岡山県立大学建築学科准教授)の発表「片桐悠自『アルド・ロッシ 記憶の幾何学』を もっと楽しむためのアルベルティ」での指摘に負う。岡北氏は『科学的自伝』に載せられた「サンタンドレア聖堂」の丸窓の写真について、「大傘」のもたらす光と、「時間-環境(テンポ)」の関係を論じた。氏にはこの場を借りて感謝申し上げたい。
92024年8月19日に筆者をリミニに案内いただいたイルデブランド・クレメンテ氏(Prof. Ildebrando CLEMENTE, 建築家、ボローニャ大学建築学科准教授)の指摘に負う。氏にはこの場を借りて感謝申し上げたい。
10 「ゴイトの単家族住居」の配置図図面は以下も参照。”Site map for UNI-Casa, Goito, Italy”, https://www.cca.qc.ca/en/search/details/collection/object/500808(最終アクセス 2025年3月29日)
111126: “Pegognaga. Sezione” ([s.d.]) https://collezionearchitettura.maxxi.art/patrimonio/5c6f59d3-0388-489d-b3ff-9fd87a609c71/1126-pegognaga-sezione-%5Bsd%5D(最終アクセス 2025年3月29日)
12228-1-23 // «Theoria dell’architettura» / Autor(en): Aldo Rossi / Chronologie: undatiert / Bestand: Aufsatzentwurf Ts. 10 S. / Archiviert in: S., gta archiv
以下も参照 “Tipologia, manualistica e architettura”(1966), Aldo Rossi, Scritti Scelti sull’Architettura e la Citta,1956-1972, Milan: Clup, 1975, pp.298-310