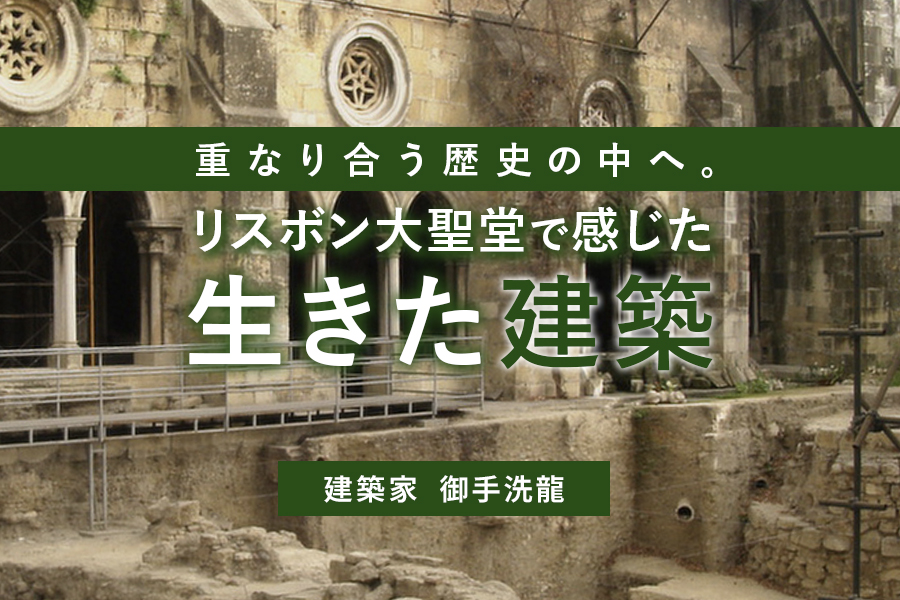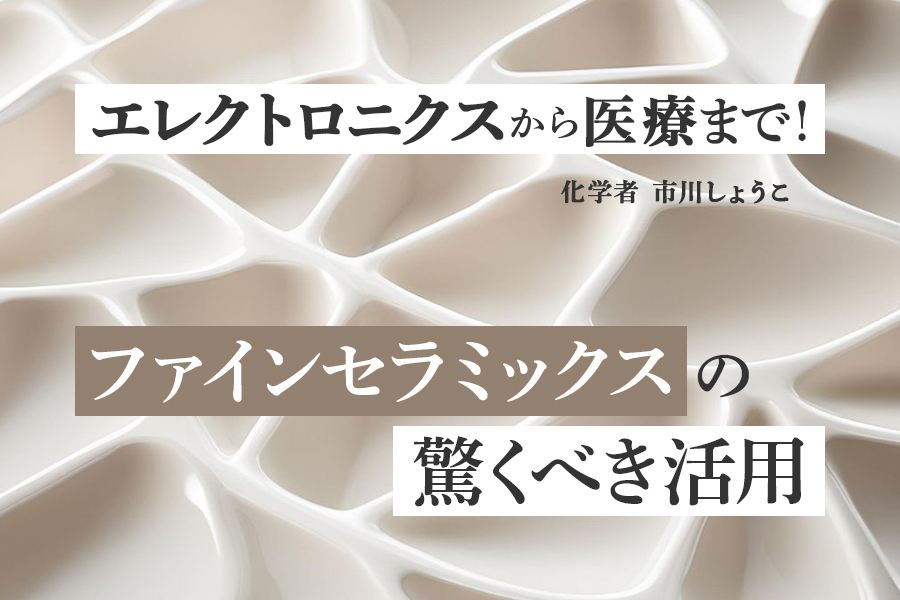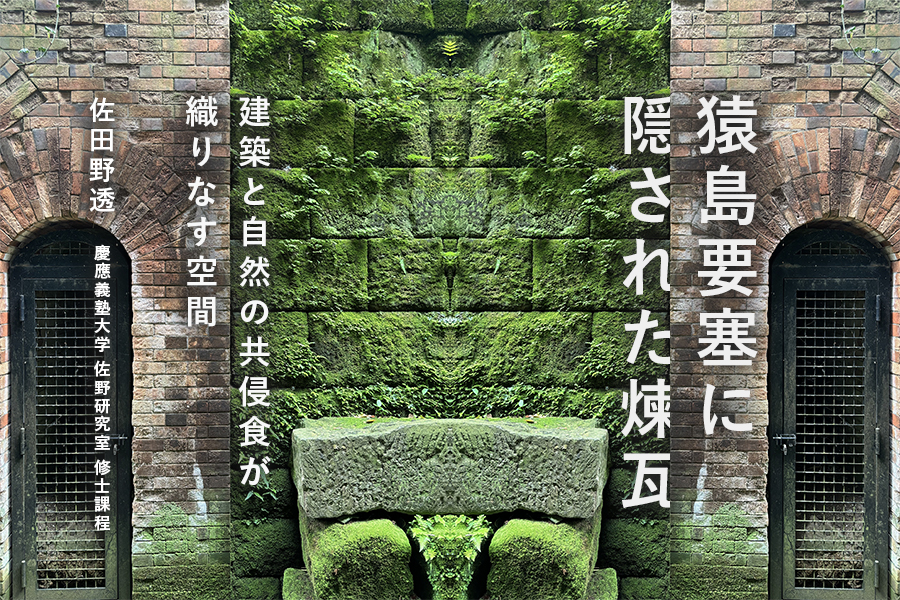焼き物を科学する⑭:夏は涼しく冬は暖かい瓦屋根(市川しょうこ/化学者)
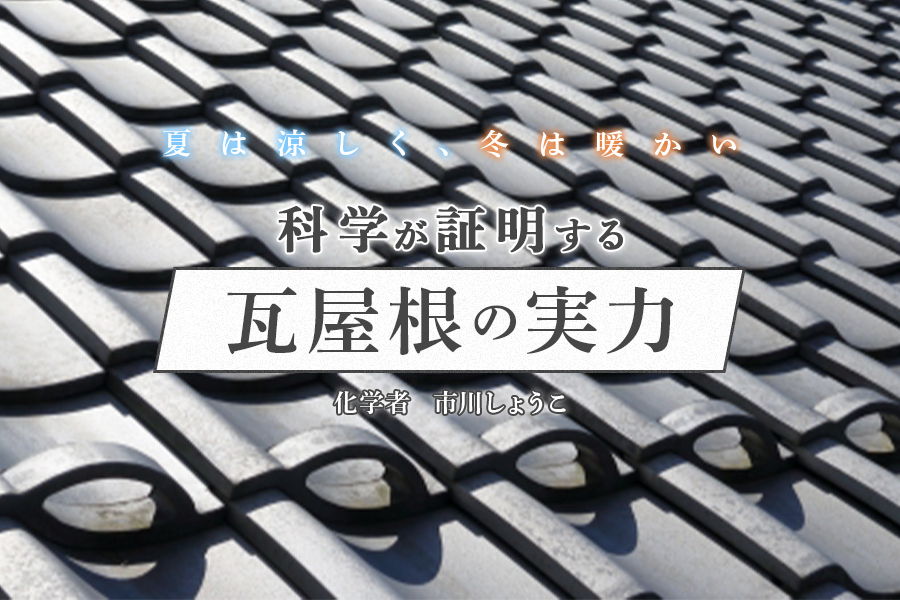
なぜ瓦屋根の家は快適なのか?
古くからある日本の町並みを見渡したとき、そこには瓦屋根の家が多く立ち並んでいます。その景色は単なる美観というだけではなく、実は人々の暮らしを支える合理的な理由に基づいたものなのです。
瓦は粘土を焼き締めた焼き物であり、内部には微細な空隙を持つ多孔質構造をしています。この構造は熱の伝わり方や、光の反射に大きな影響を与えています。例えば、夏の直射日光を受けても室内が極端に暑くならないのは、瓦が赤外線を反射したり、熱をため込んで時間をかけて放出したりする性質があるためです。また冬場には、この「ため込む性質」が室内の温度を安定させる役割を果たします。近年では、JIS規格に基づいた日射反射率の測定や小屋裏温度の実測実験からも、瓦屋根が冷房負荷や暖房負荷の低減に繋がるデータが確認されています。
つまり瓦屋根は、伝統的な建築資材でありながら、現代科学で裏づけられる「天然のエアコン」とも言えるのです。今回は、瓦が持つ快適な温度を保つ性質にフォーカスして、瓦の魅力を紐解きます。
「熱伝導率」で外気の温度をカット
瓦屋根には、夏の暑さや冬の寒さが屋内に伝わることを防いでくれる効果があります。この効果に関係しているのが、「熱伝導率」です。
熱伝導率とは熱の伝わりやすさを示す指標で、数値が大きいほど熱が速く伝わり、小さいほど熱が伝わりにくいことを表します。金属は特にその値が大きく、銅で約398 W/(m・K)、アルミニウムで約237、鉄で約80とされています。金属に触れた瞬間に冷たさや熱さを感じるのはこのためです。
一方で、瓦などの焼き物の熱伝導率はわずか1.0~1.6 W/(m・K)程度しかなく、銅やアルミニウムに比べて数百倍も熱を伝えにくいのです。そのため、夏の日差しを浴びても、熱が即座に裏側まで届かず、室内が急激に熱せられることを防いでくれます。また雪が降るような寒冷地でも、冷たい空気が伝わることを防ぎ、部屋の中を暖かいまま保つことができます。
この「熱を伝えにくい」という特性が、夏の瓦屋根の家を涼しいと感じる第一の理由です。
「熱容量」でお部屋の温度が一定に
瓦屋根が快適な室温をもたらす要素には、「熱容量」もあります。先ほどの熱伝導率は熱の伝えにくさを表していた一方で、熱容量とは「どれだけ熱をため込めるか」を示す指標です。
熱容量は比熱(温度を1℃上げるために必要な熱量)と質量を掛け合わせた値です。比熱が大きいほど温まりにくく、冷めにくい性質を持ちます。金属は一般的に比熱が低く、銅が0.39 kJ/kgK、鉄が0.44と、すぐに温まりすぐに冷める特徴があります。一方で陶器は1.0 kJ/kgK以上と高く、さらに瓦自体が厚みと質量を持つため、膨大な熱を蓄えることができます。
このため夏場は涼しくなった部屋の温度が外に放出されることを防いでくれ、冬場は暖かい空気が放出されることを防いでくれます。
熱伝導率が低いおかげで外気の温度が中に伝わりにくく、熱容量が大きいおかげで内部の温度を保つことができます。瓦屋根は、外からも内からも、温度を保持することができるのです。
「赤外反射」で夏の強い日差しをはね返す
さらに、瓦には夏の日差しをはね返す性質があります。
私たちが目にする太陽光のうち、約43%が可視光線で、残りの52%以上は赤外線領域にあります。この赤外線をどれだけ反射できるかどうかが、屋根の温度上昇を左右します。
例えば「クールベーシック」といった高反射型の瓦製品では、黒色でありながら赤外線を効率的に反射します。実測では板金屋根やスレート屋根の5倍以上の反射性能を示します。同じ黒色の屋根でも、サーモグラフィーからは表面温度の差が一目でわかります。
つまり、落ち着いた色合いを維持しながら、赤外線だけを効率よく跳ね返すことで、夏の室温上昇を抑えることができるのです。
黒瓦・銀瓦・釉薬瓦で変わる温度挙動
また、一口に瓦と言っても、その表面仕上げによって温度の挙動は大きく変わります。
いぶし瓦は炭素膜による銀灰色の膜を持ちます。製造工程によって太陽光のエネルギーを反射する強さが変わり、夏場の表面温度上昇を抑える効果が確認されています。
釉薬瓦はガラス質の層によって水分を遮断し、さらに釉薬の成分によっては特定波長の光を反射するため、光沢のある表面が温度挙動を左右します。
このように「銀・釉薬の色」などの見た目の違いは単なる美観の問題ではなく、物理的な温熱環境の差として現れるのです。
ヒートアイランド対策の可能性
これら瓦の特徴は、環境問題を解決する手段の一つになるかもしれません。
都市部で問題となっているヒートアイランド現象は、アスファルトや金属屋根などが熱を吸収、放射し、夜間も気温が下がらないことが一因です。高反射型(クールベーシック)の瓦屋根を導入すると、昼間に太陽光を効率よく跳ね返すだけでなく、熱容量の高さによって熱をゆっくりと放出するため、都市全体の温度上昇を抑える効果が期待されます。
環境省の実証試験でも、瓦屋根の導入による冷房エネルギー削減効果が確認されており、都市環境改善の一手として研究が進められています。瓦屋根は単なる建材を超えて、都市の気候適応策としての役割を果たす可能性を秘めています。
自然の知恵と快適さ
瓦屋根の快適性は、先人たちの経験に基づく知恵として伝えられてきました。奈良時代の寺院建築から現代の住宅まで、瓦は1400年以上にわたり使われ続けています。その背景には、文化や美観だけではなく、熱伝導率の低さ、熱容量の高さといった、瓦の性質に対する眼差しがあったのかもしれません。
近年の実験や数値データによって、経験知として語られてきた瓦屋根の快適性が理論的に証明されつつあります。つまり瓦屋根は、自然環境に適応した「科学の伝統」とも言える存在です。今後も研究が進むことで、伝統建材の中に未来の環境技術のヒントを見出すことができるのではないでしょうか。
【出典・参考文献一覧】
瓦用釉薬の日射反射率の測定、島根県産業技術センター研究報告 第46号(2010)
いぶし瓦の日射反射率向上、愛媛県産業技術研究所 窯業技術センター
屋根の高断熱化と高反射化による小屋裏内温熱環境の改善、日本建築学会技術報告集(2003)