焼き物を科学する⑩:燻す焼成で、変わる発色
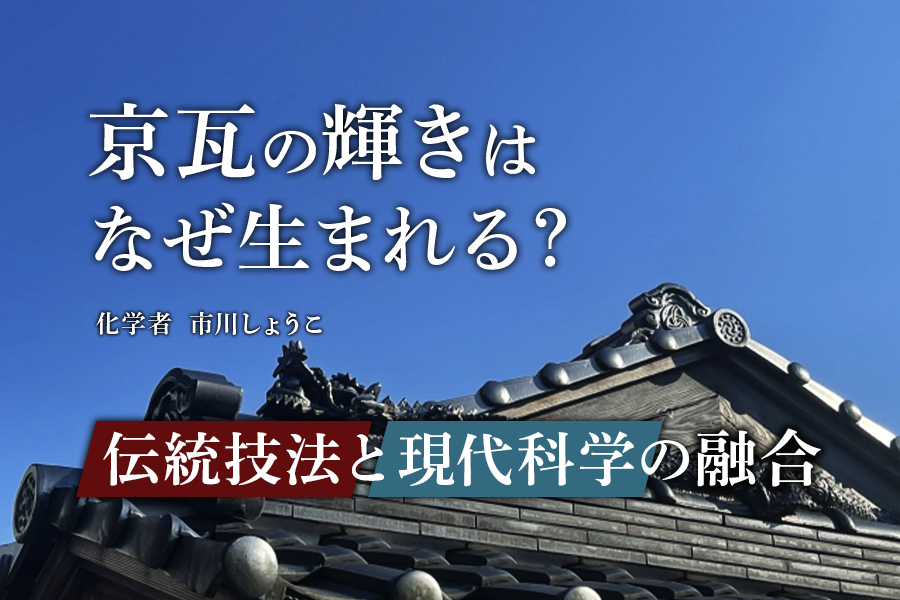
1.焼き物を「燻(いぶ)す」
焼き物の魅力は、形や模様だけにとどまりません。実は、焼成の方法ひとつで、色合いや表情は大きく変わります。中でも「燻(いぶ)し焼成」と呼ばれる手法は、焼き物に独特の風合いや色合いをもたらす、奥深い技法のひとつです。
みなさんは京都に行ったことがありますか?実は、京都の寺院や古い建築物に使用されている瓦の多くは、銀灰色の光沢がある燻し瓦というものです。その名称自体は、聞きなじみがないかもしれませんが、京都の街並みを歩いていたら、一度は目にしているはずです。
炎と煙に包まれた窯の中で、酸素を制限して焼かれることで、燻し瓦の表面には金属的な光沢や黒褐色の渋みが現れます。これは、一般的な酸化焼成や還元焼成とは異なる、特有の化学反応が関与しています。目に見える変化の背後には、複雑な素材の変化や化学反応が隠れています。
本記事では、燻し焼成がどのような技法であり、なぜ焼き物の発色を変えるのかを、科学的な視点と芸術的な魅力の両面から解説していきます。焼き物に込められた「煙の魔法」を紐解いていきましょう。
2.燻し焼成とは?
焼き物の世界では、「火」は単なる熱源にとどまらず、器の表情を決定づける要素の一つです。その中でも燻し焼成は、酸素を遮断した還元的な環境で焼成する技法であり、陶器に独特の色彩や風合いをもたらします。代表的な例としては、備前焼の黒い斑点や、炭化焼成された瓦の銀色の光沢が挙げられます。
燻し焼成は、単に焼くのではなく、焼成雰囲気を操ることによって、化学反応を巧みに引き起こします。酸素の量や燃料の種類、焼成時間のわずかな違いが、器の色彩や質感に大きな影響を与えるのです。こうした技法は一見アナログで感覚的にも見えますが、その背景には明確な化学的メカニズムが存在しています。
還元焼成では、窯内の酸素が不足した状態を意図的につくり出します。これにより、鉄分は酸化鉄(FeO)や金属鉄(Fe)に変化し、黒や青、灰色といった深みのある色合いになります。銅を含む釉薬が赤や緑に変化するのも還元雰囲気ならではの現象です。
つまり、同じ原料を使っていても、焼成雰囲気を変えるだけで、まったく異なる風合いの焼き物が生まれるのです。
3.炭素の正体:器に染み込む化学反応
燻し焼成におけるキーワードのひとつが炭素です。焼成中に籾殻(もみがら)や木炭が燃えることで、窯の中には一酸化炭素(CO)や炭素(C)が豊富に存在する状態が生まれます。
高温下では、この炭素が陶器の表面、あるいは釉薬と反応し、発色を変化させる化学反応が起こります。たとえば、表面の鉄分が炭素と反応して還元されると、酸化鉄(赤褐色)が金属鉄や酸化第一鉄(黒~青灰色)に変化します。この変化は器の深層にまで及び、表面だけでなく、質感や強度にも影響を与えます。
また、釉薬中の成分と炭素の反応によって、微細な金属粒子が析出し、金属光沢を帯びることもあります。「火の中で還元されながら彩色される」ことで、陶器に命が吹き込まれるのです。
4.燻し焼成の伝統
日本の焼き物文化には、地域ごとに独自の燻し焼成技法が発展してきました。とりわけ有名なのが備前焼、信楽焼、丹波焼です。
備前焼は釉薬を用いず、薪窯の中で長時間焼成することで、赤茶色の地肌に黒や白の斑点模様が浮かび上がります。これらの模様は、松の灰や炭が器に付着し、燻されたことによって生じたものです。特に胡麻や緋襷(ひだすき)と呼ばれる模様は、薪の成分や酸素の遮断によって偶然的に現れるものですが、そういった状態を読み取る職人の経験も技の一部です。
信楽焼は、籾殻や藁を用いた燻しによって、焼き締めの表面に炭素が浸透し、独特の黒灰色のトーンを演出します。焼成時の温度と時間、燃料の投入タイミングなど、細かな調整がその色合いを左右します。
5.燻し焼成の代表、京瓦
全国的に見ると、燻し瓦の生産量は粘土瓦全体の約20%と多くありません。一方で冒頭でも触れた通り、瓦屋根の古い建築物や寺院が並ぶ京都の街並みは、燻し焼成によって光沢をもった銀灰色の燻し瓦によって成り立っています。そのため、これらは「京瓦」とも呼ばれています。京瓦は、社寺仏閣などの歴史的建築物でよく見られます。瓦粘土を成形し、乾燥させた後に高温で焼成し、さらに燻す工程(燻化)を加えることで、表面に炭素膜が形成された瓦です。この炭素膜により、京瓦は独特の銀色や黒色に仕上がり、「銀色瓦」や「黒瓦」とも呼ばれています。
さらに興味深いのは、この磨き工程が見た目の美しさだけでなく、機能性にも大きく貢献している点です。磨きをしっかり施した瓦ほど、燻化時に炭素膜が均一に定着しやすくなり、その結果として防水性や耐久性が高まることが知られています。
京瓦の特徴のひとつが、表面の光沢感です。この光沢にはランクがあり、上から順に「本ウス」「磨き」「並」と分類されています。なかでも磨き工程は、乾燥の途中段階で、まだ柔らかい瓦の表面をヘラで丁寧にこすって滑らかに仕上げる伝統技法です。これによって、瓦独特の艶やかな光沢が生まれるのです。
実際に、磨きを施した瓦の表面をX線回折装置という分析機器で観察してみると、「水撫で」や磨きといった作業を通して、瓦表面の粘土粒子が一定の方向に整列していることが確認されています。元の粘土の状態では粒子がランダムに分布していますが、水撫でによって粘土成分が浮き上がり、さらに磨かれることで粒子が配列されると考えられます。
このように、粒子の配向を意識せずに使いこなしていた職人たちの技術は、まさに伝統と科学の融合と言えるでしょう。実はこの「粒子の配向」は、現代のファインセラミックス技術においても重要な工程とされています。長年にわたり培われてきた伝統技法が、無意識のうちに高度な材料科学と重なっていたということに、職人技そのものの科学性を感じます。
燻し瓦の最大の特徴は、その表面に形成される微細な炭素膜にあります。この炭素膜は、瓦を高温で焼成した後、燻すことで自然に付着するものですが、近年、電子顕微鏡を用いた分析により、興味深い事実が明らかになってきました。
それは、炭素が平面状炭素として規則正しく並んでいることです。これは、まるで薄いフィルムのように炭素が層をなして広がる構造で、一般的な炭素の付着とは異なり、極めて整った分子レベルの配列を示しています。この平面状炭素がきれいに形成されるかどうかは、実は焼成前の素地(そじ)の表面がどれだけ滑らかかに大きく依存しています。表面が滑らかであるほど、炭素は美しく整列し、均一な膜をつくることができるのです。
京瓦では、こうした滑らかな素地をつくるために磨きという伝統技術が用いられてきました。本来、この磨きの工程は表面の凸凹を取り除き、見た目に美しく仕上げるためのものでした。しかし、実際にはこの工程によって炭素粒子の配向性が高まり、結果的に燻し瓦ならではの銀色の光沢や優れた防水性能が得られていたのです。
このような粒子の配向制御は、現代では半導体や先端材料の分野で薄膜を形成するために欠かせない技術とされています。つまり、瓦づくりにおいて何世代にもわたって受け継がれてきた磨きという伝統技術は、先端科学の観点から見てもひじょうに理にかなったプロセスであることがわかりました。
伝統と最先端が、時代を超えて静かに交差していた、興味深い事例です。
6.煙の中に宿る美
燻し焼成は、科学の中で生まれた偶然という名の芸術と言えるでしょう。火と煙、そして人の手がつくり出す、自然と化学が交差する奥深いプロセスです。木炭や籾殻から発生する煙が、焼き上がった陶器や瓦の表面に炭素の薄膜をまとわせ、まるで金属のような光沢を与える。そこには、色彩の変化だけでなく、防水性や耐久性といった実用的な機能も付加されています。
焼成雰囲気を変えることで、素材の中に眠る色彩や質感を引き出し、ゆらぐ煙と炎がひとつとして同じものがない表現を生み出します。焼き物における色は、単なる装飾ではなく、炎と物質と人の知恵が織りなす、科学的かつ詩的な成果なのです。
【出典・参考文献一覧】
塩野 剛司, 伝統技術に学ぶ-京瓦との出会い, 繊維機械学会誌, 2007年







