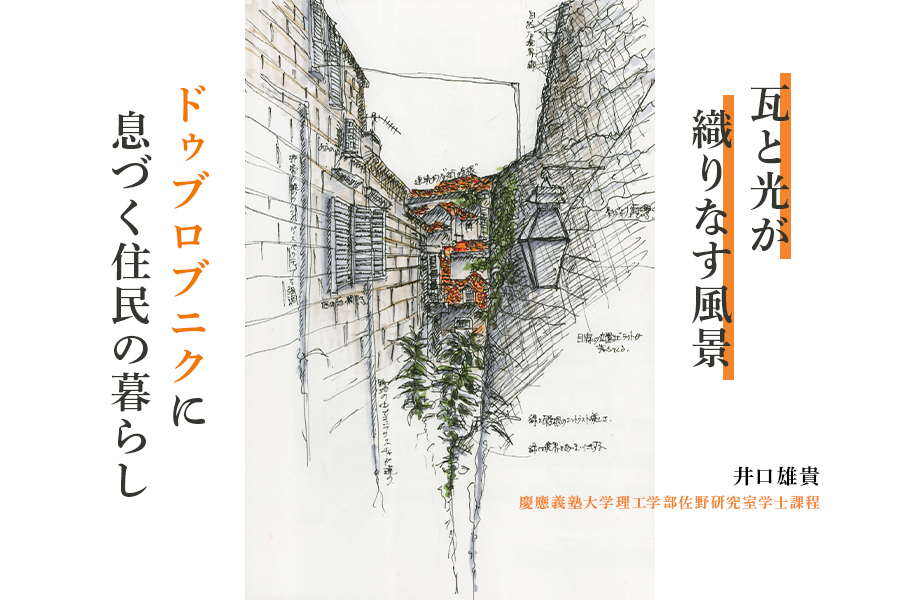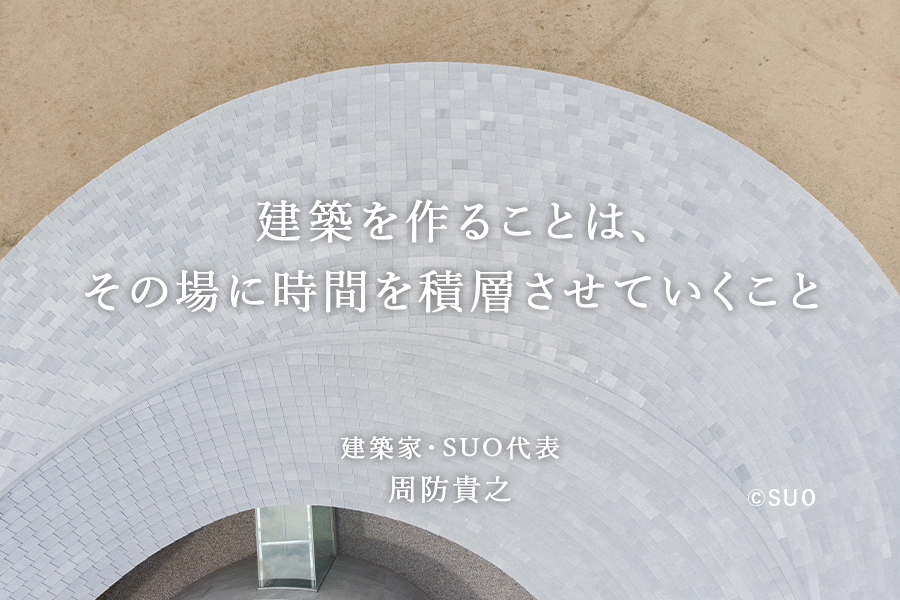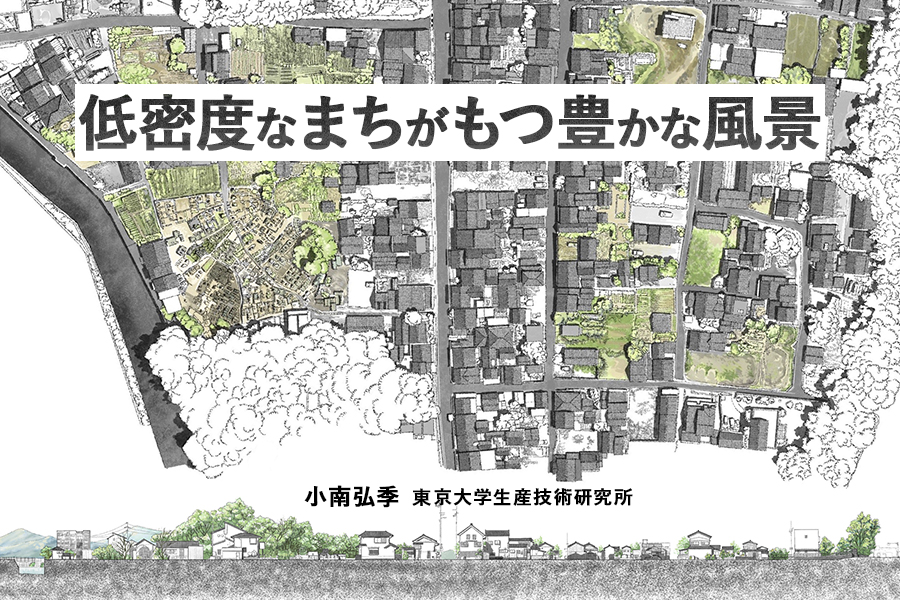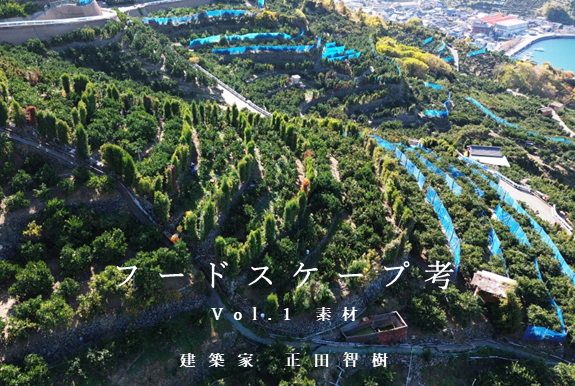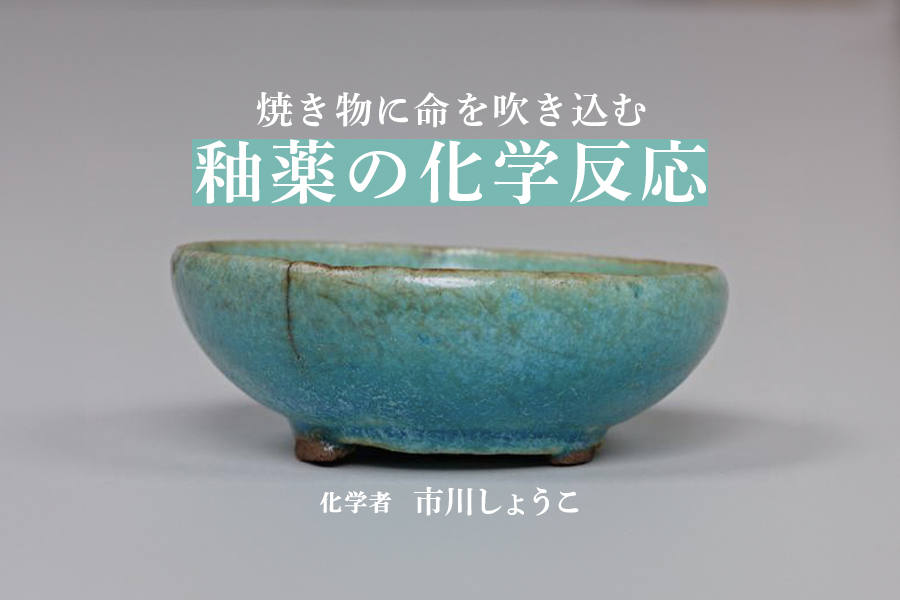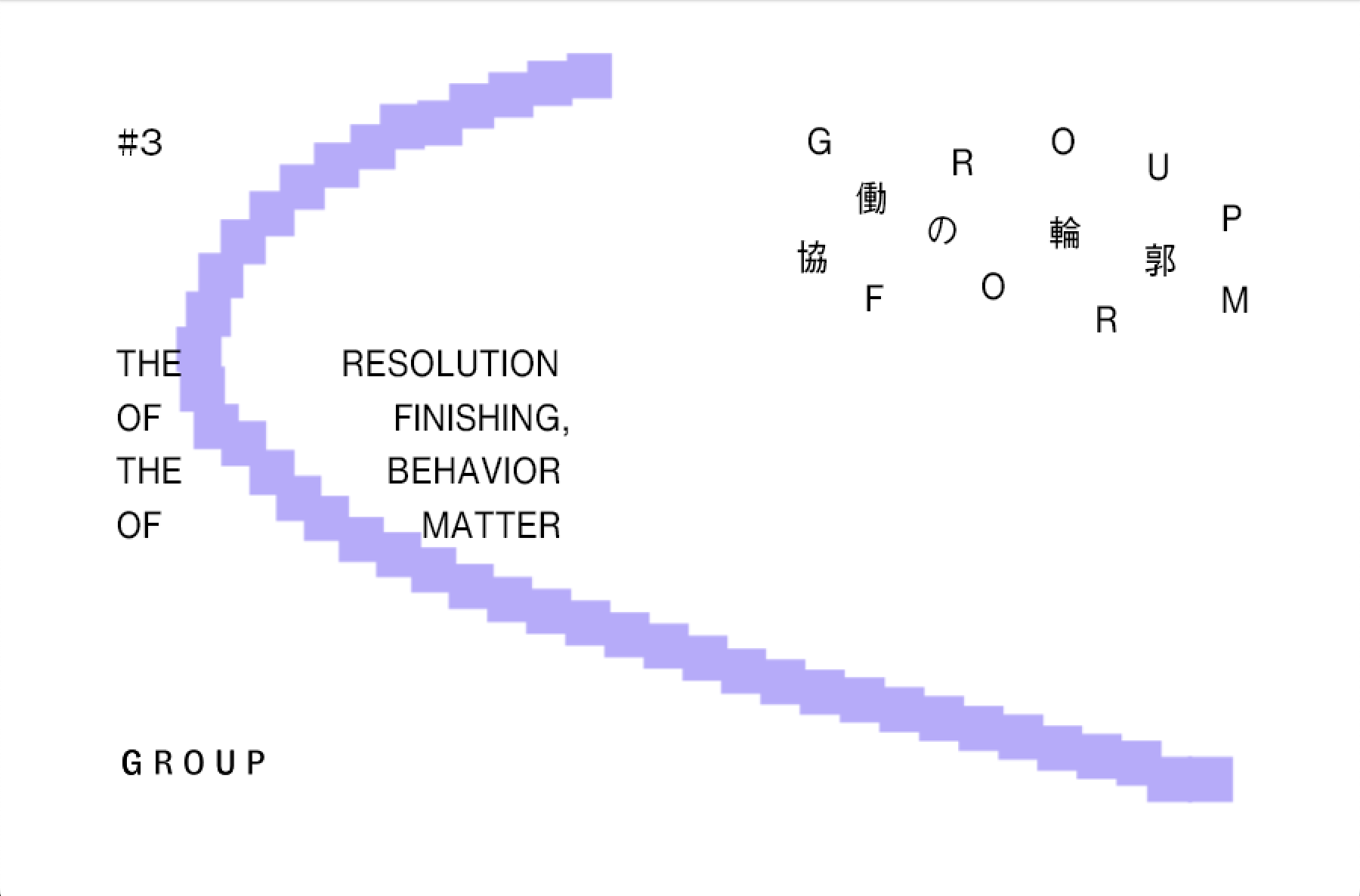劇場の扉を開くたび、音が変える世界(竹島舞/日本女子大学大学院建築デザイン研究科 キャズ・T・ヨネダ研究室修士課程)

劇場の扉をくぐるとき
劇場の扉をくぐるたび、私はいつも胸の奥が少し高鳴る。そこに待っているのは、舞台芸術という意味では同じものだが、座席に腰を下ろした瞬間に広がる世界は、劇場ごとに驚くほど異なっている。劇団四季の専用劇場は舞台と客席の距離が近く、役者の声が息づかいと共に耳元へ届く。新国立劇場や東京文化会館の大ホールにおいては、音は天井へと舞い上がり、壁や天井に反射して幾層にも重なりながら心の奥に染み渡っていく。
同じ「物語」を観ているはずなのに、建築と音響が織りなす空間の質感が、私の感覚を根本から変えてしまう。身体が包み込まれるような親密感と、遠景から見守るような視野の広がり。劇場という建築は、舞台芸術をただ収める「箱」ではなく、さまざまな体験を生み出す「器」なのだと実感する瞬間である。

建築規模と音響設計
舞台と私を繋ぐさまざまな体験を理解するためには、劇場ごとの建築規模や音響設計を見比べる必要がある。例えば、東京文化会館大ホールは約2,300席を有し、残響時間は満席時で約1,8秒と記録されている。東京文化会館1(Nagata Acoustics)この残響の厚みは、クラシック音楽やオペラにふさわしい「豊かな音の層」を生む。音は空間を漂い、反射と減衰を繰り返しながら観客に届くため、直接的な声の鮮明さよりも、外側から物語を眺めるような感覚を観客に与える。

一方で、劇団四季の専用劇場(海、秋)は約1,200〜1,500席とコンパクトで、残響は短めに設計されている。公式サイトでは座席数のみが公表されているが[劇団四季専用劇場](海、秋)、音響設計に関しては、どの席からも舞台の細部が見やすく、台詞や歌詞が鮮明に届くことが重視されているという。残響よりも明瞭さを優先した空間づくりが、観客と舞台の一体感を生み出しているのだ。
新国立劇場(オペラパレス)の体験談
初めて新国立劇場のオペラパレスに足を踏み入れたとき、私はその「高さ」に圧倒された。天井はおよそ54メートルにも達し、舞台を包み込むように馬蹄形の空間が広がっている。深い赤の座席、木質パネルが重なり合う壁面。視覚的な荘厳さと同時に、音響的な工夫が随所に隠されている。
歌声やオーケストラの響きは、ある一点から耳に届くのではなく、空間全体をさまよいながら降り注ぐようだ。音は天井まで舞い上がり、やわらかに反射し、重層的に広がっていく。観客一人一人に「直接」届くと言うよりも、空気そのものに溶けていく響きを一緒に浴びているような感覚だ。気づけば私は「個」として舞台を見るのではなく、「空間の一部」として物語を受け取っていた。

オペラパレスは約1,800席、残響時間は満席時で1,4〜1,5秒。新国立劇場2オーク材のパネルが音を適度に拡散させ、響きの濁りを防ぎつつ、豊かさを損なわない。この設計が、オペラやバレエにふさわしい「空間の広がり」を実現しているのだろう。
ここでは「近さ」ではなく「響きの重なり」が体験の中心になるのではないかと考える。私は舞台の一員になるのではなく、大きな響きの一部として存在している。舞台を観るというよりも、空間と響きに身を委ねるという体験。それがオペラパレスの魅力である。
四季劇場(海、秋)の体験談
四季劇場に入ったときにまず感じるのは「近さ」だ。初めて友人に連れて行ってもらった時、座席表を見ながら「ちょっと遠い席かも」と謝られた。しかし実際に座ってみると、舞台との近さに驚いた。役者の息遣いが直接届くようだった。

電通四季劇場[海]は約1,200席、JR東日本四季劇場[秋]は約1,500席。劇団四季3新国立劇場や東京文化会館に比べて規模は小さい。座席は扇状に配置され、舞台と客席の間に余白はほとんどない。ここでは音が残響に包まれるのではなく、まっすぐに耳へ届く。吸音材と拡散材のバランスによって反響は抑えられ、台詞や歌詞の明瞭さが優先されていると考える。結果として、観客は音の層に浸るのではなく、「声そのものの鮮明さ」に没入する。
劇団四季の公式方針に「どの席からも舞台の細部まで見やすい」という理念が掲げられているように、この劇場は視覚と聴覚の一体化を重視している。舞台と客席の物理的距離の短さは、身体的距離の短さにも直結する。役者の声に包まれるのではなく、役者と呼吸を共有する感覚。それこそが、四季劇場ならではの体験なのではないのだろうか。
物語の幕が下りたあとの静けさ
物語の幕が下りた後、客席に広がる静けさの中で、私は改めて考える。劇場とは、単に演者を照らすライトや舞台装置を収めた建築ではなく、音と空間と素材が観客の心を受け止める「器」なのだと。
新国立劇場や東京文化会館では、残響の重層性が観客に静謐さと崇高さを与える。音は建築の中で反射と拡散を繰り返し、やがて一歩身を引いたところから物語をみる感覚をもたらす。一方、四季劇場では、言葉や歌の鮮明さが優先され、人の息遣いを間近に感じることができる。近さゆえの没入は、舞台と観客の境界を溶かしてしまう。
この二つの体験は常にある問いを私に投げかけてくる。舞台は芸術をただ「観るためのものではなく、身体で受け止め、心で共鳴させるためのもの。受身」ではなく能動的に感じるもの。そしてその共鳴を、建築という「器」がどこまで意識的にデザインできるのか。空間の質感が、人の心に与える影響は計り知れないものである。
私の問いはここにある。劇場を設計することは、物語そのものを設計することと同義なのではないか。そして未来の建築において、私たちがどのように「人と物語の距離」をデザインしていくのかが、重要になってくるのではないのだろうか。

【出典・参考文献一覧】