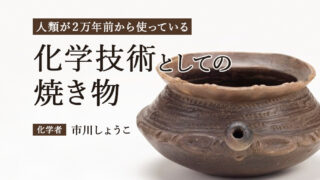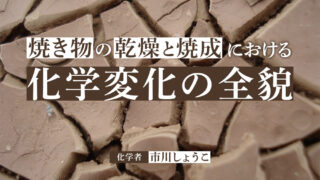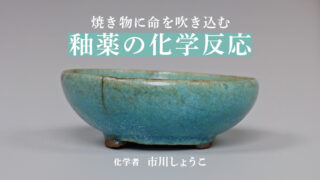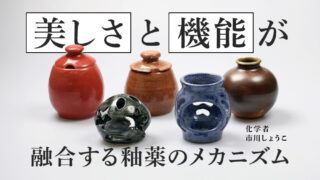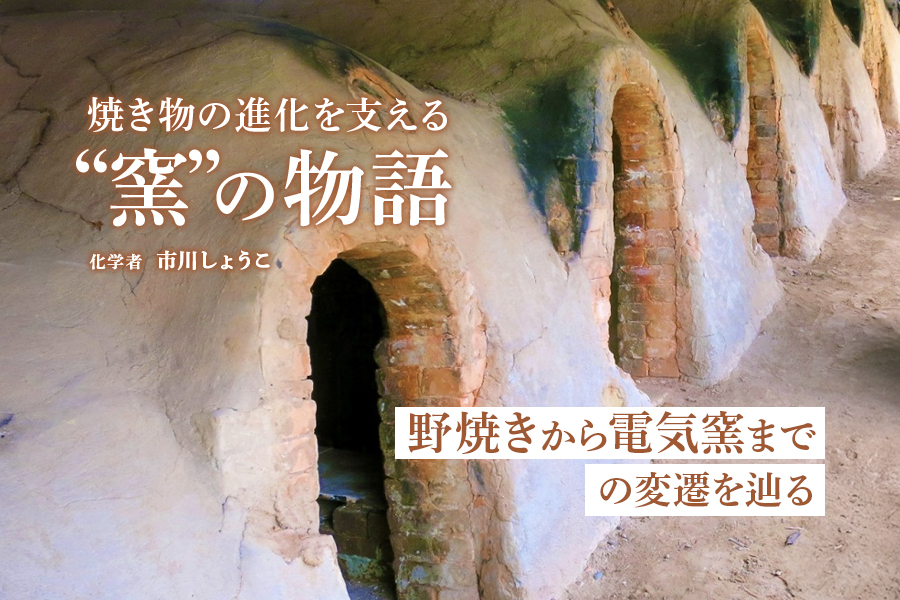焼き物を科学する⑨:化学で読み解く磁器と陶器の違い(市川しょうこ/化学者)

1.2種類の焼き物、陶器と磁器
焼き物は「陶磁器」と呼ばれることがあります。陶磁器とは「陶器」と「磁器」の総称です。どちらも土や石などの自然物を原料とし、高温で焼成することで硬く丈夫になりますが、それぞれに異なる特徴を持っています。
陶器は、主に粘土を原料とし、多孔質で温かみのある質感が特徴です。古くから日常的な器として親しまれ、日本の伝統的な焼き物にも多く見られます。一方、磁器は陶石と呼ばれる岩石を砕いて作られ、ガラス質を多く含むため、硬く滑らかで透光性があります。西洋の高級食器や美術品にも多く用いられています。
このように、陶磁器は特性によって用途や価値が異なります。本記事では、「原料」「焼成」「結晶構造」の3つの視点から、磁器と陶器の違いを詳しく解説し、陶磁器の魅力に迫っていきます。
2.原料の違い
陶器と磁器の大きな違いのひとつに、原料があります。どちらも土や鉱物のような自然物を主成分としていますが、性質が異なるため焼き上がったときの特徴に大きな違いが生まれます。
陶器は、主に「粘土」を原料としています。粘土は、長い年月をかけて岩石が風化し、細かい粒子となったものです。この粘土には、ケイ酸(SiO₂)、アルミナ(Al₂O₃)、水分などが含まれています。水を加えると柔らかく成形しやすくなり、ろくろや手などさまざまな方法で加工ができます。焼成すると、水分が蒸発し、粘土の粒子が結びついて固まります。内部には細かい気孔が残るため、水を吸いやすく、釉薬をかけないとややざらついた質感になります。
また、陶器の原料には鉄分が多く含まれていることが多く、これが焼成後の色に影響を与えます。陶器独特の温かみのある風合いや、土地ごとの焼き色の違いを生み出します。
一方、磁器は「陶石(とうせき)」と呼ばれる岩石を砕いて作られます。陶石は、長石、石英、カオリナイト(カオリン)などを主成分とする鉱物です。これらは、粘土よりも粒子が細かく、純度が高いため、焼成するとガラスのように緻密で硬くなります。ガラスほど透明にはなりませんが、光をあてると透ける透光性を持ちます。
特にカオリナイト(Al₂Si₂O₅(OH)₄)は、磁器の形成に重要な役割を果たします。カオリナイトは高温で焼成されると化学変化を起こし、強度のある構造に変化する鉱物です。また、長石は焼成時に溶けてガラス質となり、磁器の表面を滑らかにします。このため、磁器は水を吸わず、硬くて光沢のある仕上がりになります。
このように、原料の違いが、見た目や使い勝手に大きな影響を与えます。
3.焼成温度の違い
焼成温度の違いも、陶器と磁器の違いを生む大きな要因のひとつです。陶器も磁器も、原料を高温で焼くことで強度を高めます。しかし、陶器と磁器では使用する原料が異なるため、適した焼成温度にも違いがあります。
陶器は、900~1,200℃程度の温度で焼成されます。比較的低い温度で焼かれるため、原料の粘土が完全にガラス化せず、内部に微細な穴が多い多孔質な状態になります。
また、焼成方法によって、粘土中に含まれる鉄分や不純物がさまざまな色に発色し、独特の表情を生み出します。例えば、日本の「信楽焼」や「備前焼」は、焼成中に酸化や還元の状態が変化することで多彩な風合いを持っています。古くからある日本の焼き物は、ほとんどが陶器です。
磁器は、1,200~1,400℃程度と、陶器より高温で焼成されます。この高温により、原料の長石が溶けてガラス化し、磁器特有の硬く緻密な質感を生み出します。さらに、磁器が持つ透光性は、焼成時に気孔がほとんどなくなるためです。
また、高温焼成によって、磁器は吸水性がほぼゼロになり、水や油を通さないため、食器として非常に実用的です。そのため、中国の青白磁や日本の有田焼など、高温で焼かれる磁器は世界中で愛用されています。
このように、低温で焼かれる陶器は温かみのある質感を持ち、高温で焼かれる磁器は滑らかで丈夫な仕上がりになります。
4.結晶構造の違い
陶器と磁器の違いは、見た目や触り心地だけではありません。実は、原料が焼成される過程で形成される「結晶構造」にも大きな違いが生じます。結晶構造とは、物質の原子や分子がどのように並んでいるかを示すもので、これが陶磁器の強度、吸水性、透光性などの特性を決定づけています。
陶器の結晶構造の中で特に重要なのは、「ムライト」と呼ばれる針状の結晶です。焼成が進むにつれ、粘土に含まれるカオリンが分解し、ムライトが形成されます。ムライトは陶器の強度をある程度高めますが、その量は多くないため、全体としては比較的脆い性質を持っています。
また、陶器には石英も多く含まれています。石英は熱膨張率が高く、温度変化によって膨張・収縮しやすいため、陶器は熱衝撃に弱い傾向があります。
さらに、焼成の過程で一部の成分が溶け、冷却時にガラス化することで「ガラス相」が生じます。しかし、陶器の場合は焼成温度が低いため、このガラス化は部分的にしか進まず、全体的に多孔質の構造が維持されます。この構造によって、陶器は温かみのある質感となり、また素朴で自然な風合いが生まれるのです。一般的に、陶器には釉薬が施され、表面をガラス質にすることで吸水性を抑え、耐久性を向上させる工夫がされています。
磁器は1,200~1,400℃と、陶器より高温で焼成されますが、この高温焼成によって、原料の結晶構造が大きく変化し、磁器特有の緻密な構造が形成されます。
磁器の焼成過程では、陶器と同じくムライトが形成されますが、その量が圧倒的に多くなります。ムライトは細長い針状の結晶であり、高温焼成の結果として磁器内部にしっかりと形成されることで、全体の強度を大幅に向上させます。また、磁器には「クリストバライト」と呼ばれる石英の変成結晶も含まれています。クリストバライトは熱膨張率が低いため、磁器は温度変化に強くなり、急激な温度変化によって割れにくいという特性を持つようになります。
さらに、磁器の特徴的な性質を生み出しているのが、焼成によって広く形成されるガラス相です。磁器には長石が多く含まれており、これが高温で完全に溶けることで、大量のガラス相が生じます。このガラス相が磁器の構造を緻密にし、吸水性をほぼゼロにする役割を果たしています。また、ガラス相の屈折率によって磁器は光を通す性質を持ち、透光性が生まれます。これが、磁器特有の滑らかで光沢のある表面や、美しい白色の仕上がりにつながっているのです。
5.性質の違いが生活に彩りをもたらす
このように、陶器と磁器は、原料や焼成過程、そのなかで起こる化学的な構造から、特性が決まっています。これらの違いは、陶磁器の使い方や文化にも大きな影響を与えてきました。陶器は吸水性があるため、日本の茶道具や土鍋などで活用されてきました。一方、磁器は強度が高く吸水性がほぼゼロであるため、高級食器や医療・電気産業など幅広い分野で利用されています。陶磁器は、単なる道具ではなく、科学と文化が融合した結晶のような存在です。シーンに合わせて好みの焼き物を選ぶと、日々の生活により彩りをもたらしてくれるかもしれません。
参考文献
陶磁器の化学、矢田 光徳、化学と教育、2023年