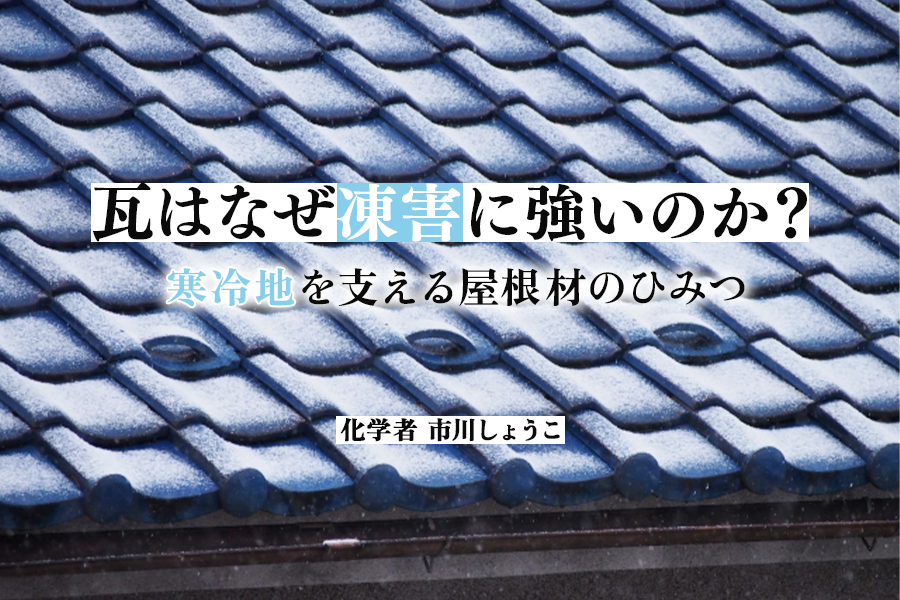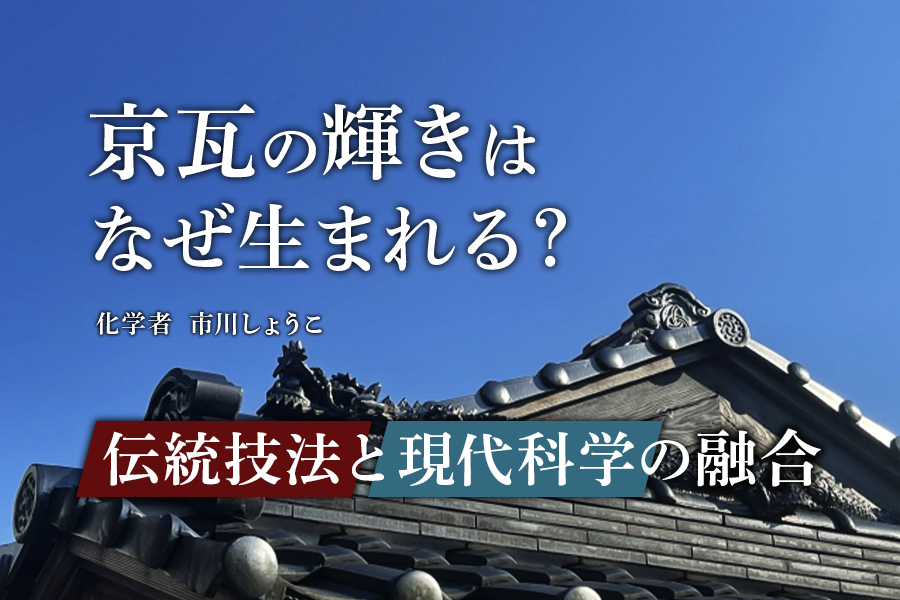建築行脚#02「リスボン大聖堂とファドの夜」(御手洗龍/建築家)

2003年3月9日、リスボン2日目。
旅の初日だった前日、ポルトガルの太陽をしっかり浴びたおかげか、あるいはぐっすり眠れたからか、時差ぼけも感じない。朝から軽やかな足取りで街を歩き始めた。窓の外には洗濯物を干すお母さんたちの姿があり、朝陽を浴びる猫が窓辺で静かに時を過ごしている。石畳の路地では、玄関先に鉢植えが並び、ふと見上げると窓台やペントハウスの庭からあふれる花々が太陽に向かって伸びをしているように見えた。

リスボンの街は坂道や階段のある路地が多く、ふとした街角がどこも絵になる。迷路に迷い込んだかと思えば、思いがけず遠くまで視界が抜ける瞬間もあり、歩くことそのものがとても楽しい街だ。こうして歩いていると、街の大きさや構造が少しずつ身体に馴染んでくる感じがした。一人旅は初めてだったが、その新しい感覚がとても嬉しかった。

太陽が高く昇った午後、リスボン大聖堂を訪れた。リスボンで最も古い教会と書いてあったので、街の中心に広場を従えた建築を想像していたが、実際にはトラムの走る急な上り坂の途中に、それは突如として姿を現した。正面に双塔が聳え、中央にバラ窓、その下には入口としてアーチ形の大きな穴が穿たれている。それはまるでトラムをそのまま飲み込んでしまいそうな大きな口のようにも見え、思わず息を呑んだ。

建物の中に足を踏み入れると、暗く重く、荘厳で静かな空気が満ちており、屋根まで伸びる円柱が強く印象に残った。奥へ奥へと歩みを進めていくと、ふいにリブ・ヴォールトが連なる明るいゴシックの空間が現れ、その回廊に囲まれた中庭では、古代ローマやイスラム、中世の遺跡の発掘調査が行われていた。

リスボンという街は、古代ローマ時代の後、8世紀から12世紀にかけてイスラム支配を経験し、やがてキリスト教勢力に奪還され、ポルトガル王国の首都となった歴史をもつ。その後、大航海時代には世界貿易の中心として栄え、そうした幾層もの時間を抱えたまま現代へと続いている。
リスボン大聖堂は建築様式が混在しているだけでなく、遺跡を守る鉄骨屋根の下に、ローマ時代の壁やイスラム時代の階段が下敷きのように織り込まれている。時代や様式が塗り重ねられながら時間が蓄積していくその姿は、今も静かに生き続ける、大きな生き物のように感じられた。思い返せば、この街の路地がもつ迷路のような複雑さや陰影の深さも、遠いイスラムの記憶を今なお抱え込んでいるからなのだと気づかされる。この土地に積み重なった深さと時間の層に、ただただ心が震えた。

そして陽も傾きはじめた頃、偶然にも同じ日にリスボンを旅していた友人と、4人で食事をする約束があった。予約してくれていたレストランへ向かい、坂道を下りながら、昼とは異なる表情を見せ始めた街を歩く。石畳は夕暮れの光を鈍く反射し、白い壁面にはオレンジ色の影がゆっくりと伸びていった。
店に入ると、低い天井と蝋燭の灯に包まれた薄暗い空間に、料理の匂いと人々の話し声が静かに満ちていた。ワインを注ぐ音、フォークと皿が触れ合う気配。少し大人になったような高揚感も、友人たちとのお喋りとともにゆるやかにほどけていく。温かいポルトガルの郷土料理を味わっていると、ふいに店内で拍手が沸き起こった。待ちわびていたファドが始まったのだ。丸みを帯びたポルトガルギターを二人が奏で、その横では大きなコントラバスが静かにリズムを刻む。どこか懐かしく、胸の奥に触れるような歌声が弦の響きに乗って空間いっぱいに広がっていった。

ファドはリスボンの下町で生まれた民族歌謡であり、その音楽の奥に漂う哀調は、かつてこの街に生きた人々の日常や街の姿が、形を変えて今も息づいている証のように感じられた。ファドの歌が終わり、拍手に包まれた後、再び会話に戻る中で、明日ナザレに行こうと思っている、という友人の一言があった。特に細かな予定を決めていなかったこともあり、ふいに行き先を決めるのも面白いと思い、一緒にナザレの街へ行く約束をした。
食事を終え、ほろほろとした楽しい余韻を引き連れて宿へと戻ると、窓の外には美しいリスボンの夜の街が広がっていた。通りに明かりが灯ることで、昼の建物の風景とは図と地が反転したような景色が立ち現われ、ひときわ魅力的に見えた。

明日のナザレはどんなところだろう。洗濯石鹸の香りに包まれた、少し硬いベッドの上で、そのまま深い眠りについていった。