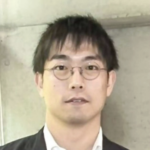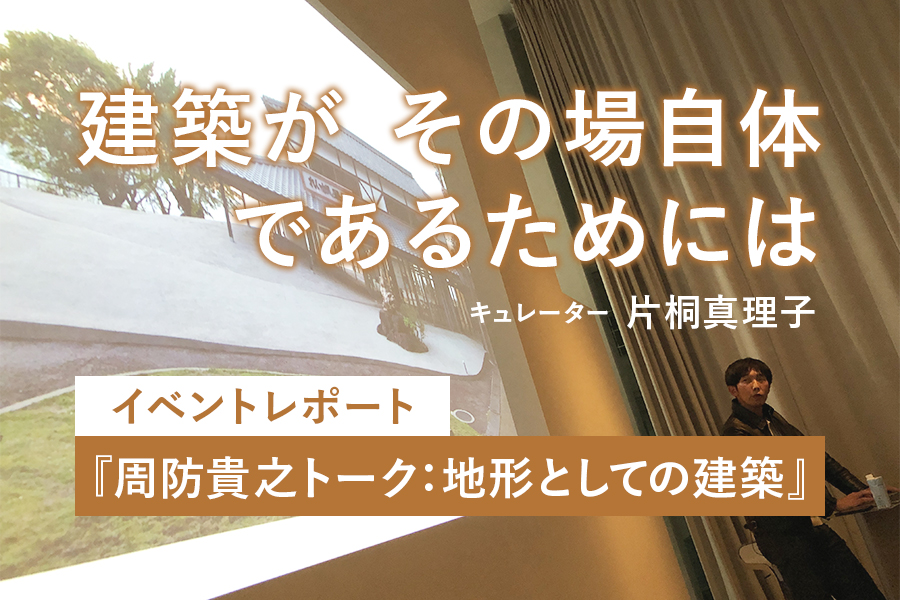創造系不動産・片山優樹による「武田清明トーク:大地と建築」イベントレポート

環境にポジティブな影響を与える人工物が存在する
今年3月にヒトツチが開催したトークイベントは、武田清明さんが建築家としての思想を築くに至った原点の話から始まりました。イギリス留学中、武田さんが研究対象としたのは、イタリアやフランスの廃墟でした。その過程で得た気づきは、「環境にポジティブな影響を与える人工物は存在する」ということです。人工物には環境を破壊する負の側面がある一方で、生物の新たな生息地となり、生物多様性を高める可能性も秘めているという考え方に至ったといいます。
所有権の二面性
「環境にポジティブな影響を与える人工物」と聞いて私が思い浮かべたのは、「所有」と「共有」の関係性でした。
近代以降、私的所有権の制度が日本で整えられてきました。この制度は個人を守る力であると同時に、他者を締め出す力でもあります。たとえば山林や農地では、かつて地域住民や登山客が自由に通行していた山道が、安全確保などを理由に閉鎖されることがあります。郊外の開発予定地でも、子どもたちの遊び場だった原っぱが売買され、フェンスで囲まれて立入禁止になることがあります。
このような「所有を突き詰めた先にある分割」が、地域の暮らしの中にあったつながりや自然へのアクセスを奪うことがあります。
公共の場の価値と課題
このような所有による分割の性質とは別の、複数で共有する場や誰もが利用できる公共空間の存在が欠かせません。これらは私的所有の制約を受けず、自由で開かれた利用を可能にします。一方で、維持管理の責任や費用負担が曖昧になりやすく、結果として荒廃したり、利用が制限されるケースも少なくありません。つまり、所有と共有はどちらか一方を理想化できるものではなく、それらのバランスをどう設計していくかが課題となります。
モデレーターの黒川彰さんとの議論をとおして、武田さんは場に対する「愛着」という視点を、次のように紹介しました。
「管理においては、誰がどう愛着を持つのかという視点が大切です。私自身、事務所のスタッフと共に土をいじり、日々の手入れから愛着が生まれることを実感しています。人々が地域を自分の庭のように感じられる仕組みづくりや、緑を介したコミュニケーションが重要な要素になると思っています」。
排斥しない所有
「環境にポジティブな影響を与える人工物」は、人間社会における所有の壁を超えて、自然や他の生物にも開かれた共有空間となるような可能性を示しています。
多くの建築活動では、自然は管理の対象とされがちです。しかし、武田さんが手がけた鶴岡邸では、屋上庭園や植栽帯を通して、自然と人工物、人間と他の生物の境界を曖昧にする設計がなされています。廃墟が新たな生態系を育むように、建築が生物のための新たな生息地を提供し、環境を豊かにしているのです。そうした、互いが響き合う環境を武田さんは作り出しています。それは「共に生きる場を創造する」という、より広い意味での共有の実践といえるでしょう。
今回のトークイベントは、土地や建物を通して人や生き物を迎え入れる「排斥しない所有」という可能性を示す場となりました。