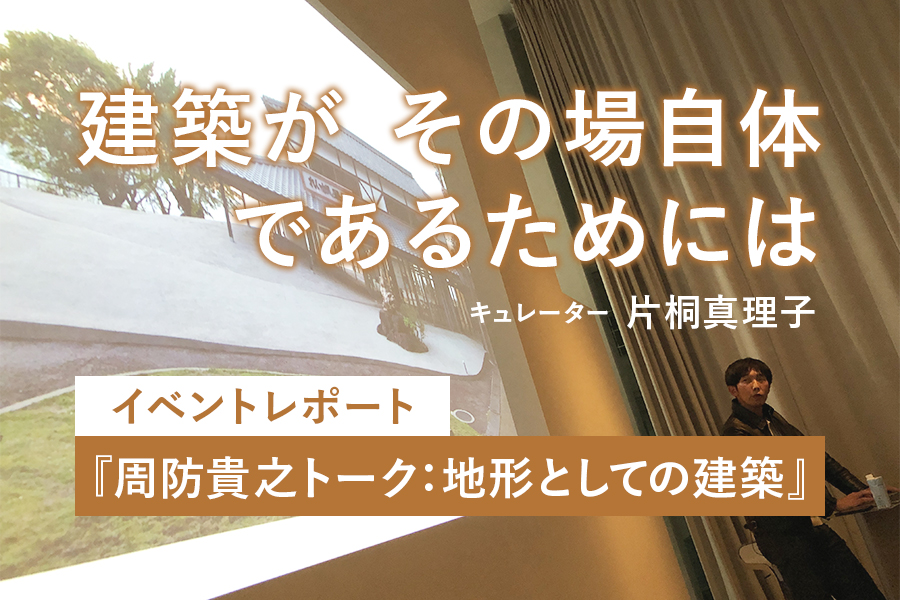建築家・上野辰太朗による「魚谷繁礼トーク:都市の時間と瓦」レポート

何が「重なって」いるのか?
昨年出版された作品集のタイトル『都市の時間を重ねる』からも分かるように、魚谷繁礼さんの建築において、都市や時間は核をなすテーマだ。「都市の時間と瓦」と題された今回のトークイベントでは、特に素材に焦点を当て、いくつかの作品が紹介された。そこで素材に注目した三つの重なりから、トークイベントを振り返ってみたい。
初めに触れたいのは、敷瓦と光の重なりである。「ガムハウス」はガム工場兼住宅であった町屋の地面が掘り下げられ、その底に敷瓦が並べられている。紹介された写真では、外壁の隙間から差し込む光が、もともと防空壕があったという町家の地下を照らし、光を受けた敷瓦が鈍く光っている。コンクリートでは明るくなりすぎてしまうという判断から敷瓦を採用したということであったが、この光の拡散具合も時間が重なるにつれ変化してゆくのだろう。時間の重なりがより顕著なのは「湯堂のある家」だ。浴槽の置かれた土間空間の床に敷瓦が使われているのだが、この敷瓦は別の建築で使われていたものの再利用だという。改修の際に設けられた格子を通して照らされた敷瓦は、新旧の境を撹乱し、さまざまな時間の重なりを現前させるメディウムとして重要な役割を果たしている。
四軒の長屋を一つの住宅へと改修した「蓮華蔵町の長屋」では、新旧を対比するのではなく、改修の積み重ねの中の一つのレイヤーとして自らの設計を扱うように意識したという。中央に新たに挿入されたコンクリートのヴォリュームは、既存の木や土壁を型枠として打設されており、経年変化で土壁が崩れると、露出した下地の竹とコンクリートが相まって見えるようになっているそうだ。そして、このコンクリート自体にも土壁の肌理が写し取られ、素材の新旧が錯綜した状態が起こるといい、具体的な重なりがデザインされていることが分かる。コンクリート、土壁、木や竹といった異なる時間軸を孕む複数の素材が、層状ではなく、複雑に重なりあう様子は、住宅という極小の都市において、都市そのものの成り立ちを暗示しているようにも思えた。
レクチャーの終盤にはいくつかの海外作品が紹介された。特に印象的だったのは、「香港の日本料理屋」の竿縁天井のように貼られた銅板であった。この銅板には、日本的なイメージと香港のキラキラとした都市のイメージを重ねて選定したそうだが、素材の物質性や時間軸にとどまらず、現象的なイメージまでを扱い、巧みに「重ねて」ゆくその自由な手法に感銘を受けた。
素材という物質的条件への言及を通して、魚谷さんの作品に通底する「重ねる」という言葉の具体性が浮かび上がってくるようなトークイベントであった。