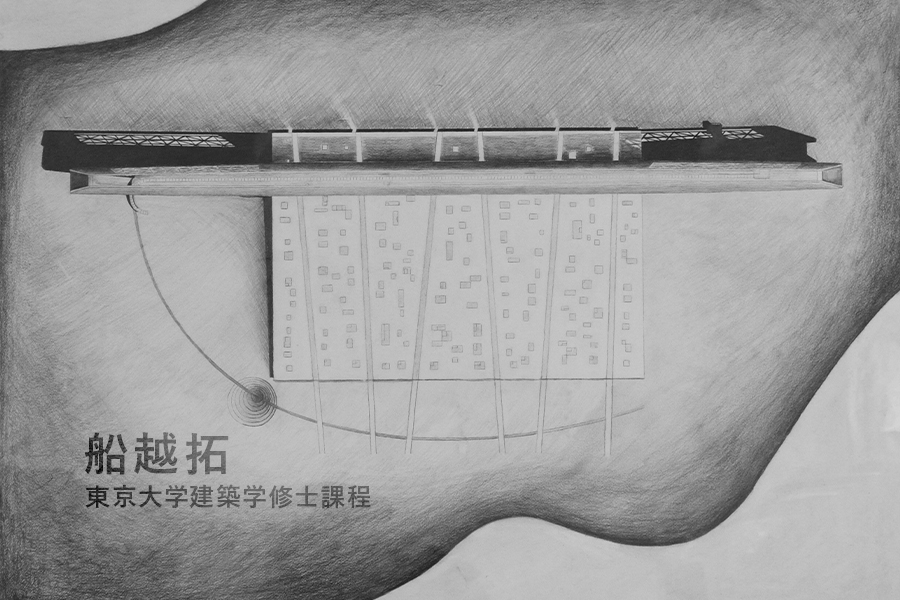都市と自然をつなぐ−植林を通して創造する「新しい森のデザイン」−(武田清明/建築家)

都市と自然、この二つのエリアは、我々の意識の中で分断され、離れつつあります。都市は「人間の暮らしの場」、自然は「他生物の暮らしの場」へとすみ分けられるようになってきました。
しかし、どんなに距離は離れていても、それらは、大地、雲、川などによって物理的につながっているし、都市の暮らしを支える建材や食材などの資源のほとんどは、自然のエリアから採取されたものばかりで、人間の一方的な視点で言うと、都市生活を成り立たせるために都市と自然はつながっていなければならないのです。
現代の都市生活は、消費すること以外の生産、収穫、運搬などのほとんどを、地方や自然エリアに外注することで、プロセスをブラックボックス化されているため、「自然の恩恵で暮らしが成り立っている」ということが、見えにくい、感じにくい状況にあります。
我々がこの問題を意識しはじめたのは、「EARTH PRODUCTS」というプロダクトデザインの活動を通して、自然と都市を頻繁に往復するようになってからです。このブランドのコンセプトとして、拾ったままの石をできるだけ加工せず室内に取り込み、ありのままのバラつきや個性をもった自然の手触り、形、色などを感じてもらうことがあったので、石拾いのために海や山など自然のエリアへ自ら足を運ぶことがとても重要だったのです。
この都市と自然の往復運動は、都市という範囲の中の狭い視野で設計活動をしてきた私たちに「俯瞰する視点」を与えてくれたと思うのです。都市で建築をデザインすること、つくることは、すでに加工された建材があることが前提ではじまります。しかし、その材料としての資源がどこから来ているのか?きっと自然の奥深くであろうその場所はどんな状況で、どんな動物や生き物が生息しているのだろう?そんな疑問がわいてきました。
これまでの都市の建築設計では、敷地、予算、周辺環境、などの条件からはじまり、それ以前の生産、加工、出荷などのプロセスまで掘り下げたところから考えることはほとんどしてきませんでした。しかし、本当の意味での建築のはじまりまでさかのぼっていくと、実は、都市と自然はつながっているということがわかります。そして、ひとつの建築を生みだすときの姿勢として、本来の「はじまり」から建築を創造してみたいと思うようになってきたのです。
それが発端で、「EARTH PRODUCTS SCHOOL」という里山型植林のワークショップを重ねることになりました。スクール/学校とは言っても、講師も先生もいない「里山型植林」の在り方をみんなで考え、つくっていく場です。学ぶ、教わるではなく、私たちの暮らしを支えている資源のはじまりの場、自然を体験して、それぞれ感じたことを都市に持ち帰ってもらいたいと思っています。
「都市で活動するデザイナーが、植林!?」と思われる方も多いかもしれませんが、地方や自然エリアこそ、デザインのアイデアを必要としています。例えば、森にはいろいろな動物が住んでいますが、現在の植林は、人間の暮らしのための建材となるスギやヒノキで埋め尽くすものばかりで、時代や周辺環境が変わっているにも関わらず植生が変わっていません。
森にはどんな生物が暮らし、何を食べているのかをリサーチし、それらの食糧を生みだす樹種を混在させたり、土砂崩れや花粉などの環境対策も考慮した植林の在り方──「新しい森のデザイン」をこれからは考えていかなければなりません。私たちの生活は、自然の恩恵で成り立っています。だからこそ、都市の暮らしのデザインだけでなく、その産地となる自然の中で生息する他生物の暮らしにも目を向け、問題に気付き、その対策となるデザインを実行し、都市と自然の相互補完関係を築いていかなければなりません。
遠く離れた敷地と産地、生産から消費までをつなぎ、都市と自然をまたぐ俯瞰の視点で、どのような新しい建築が生まれていくのかに興味がわいています。そして「都市と自然はつながっている」ということが実感できるような建築や環境のデザインをますます目指していきたいと思うようになりました。他生物が暮らす環境を都市に受け入れたり、大自然の中で人間が過ごす場所やきっかけをつくっていったり。都市と自然、人間と他生物の暮らしの間に「境界線のない世界」を目指していきたいです。


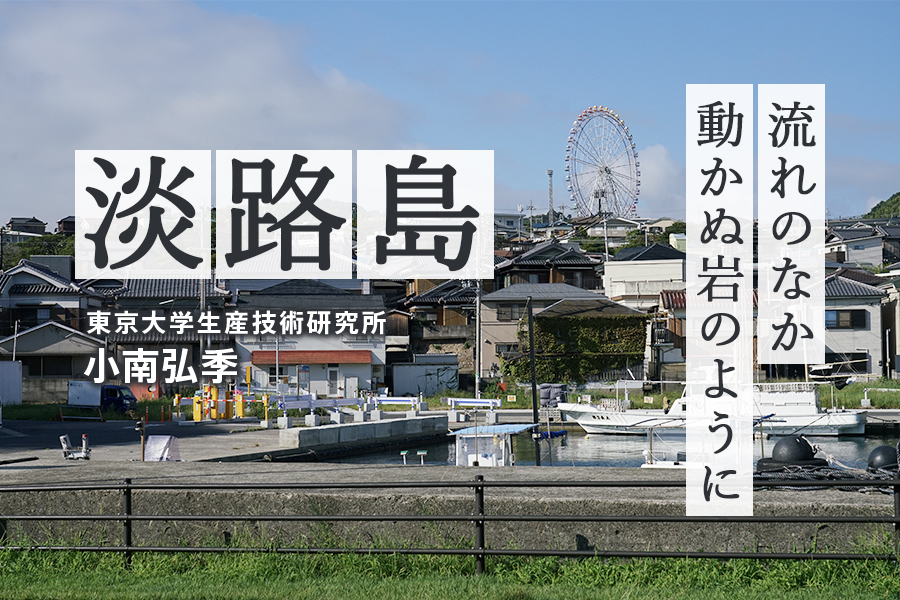
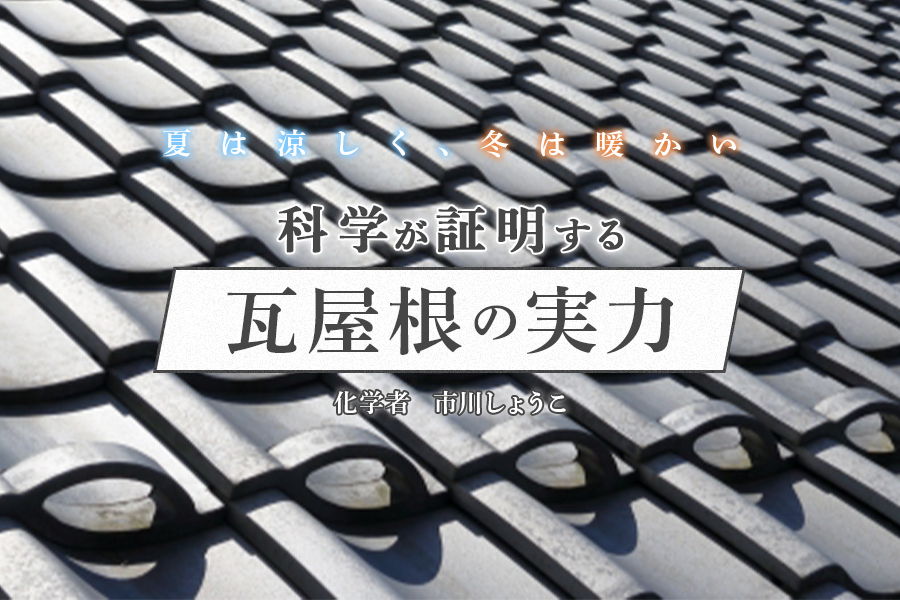

_2.jpg)