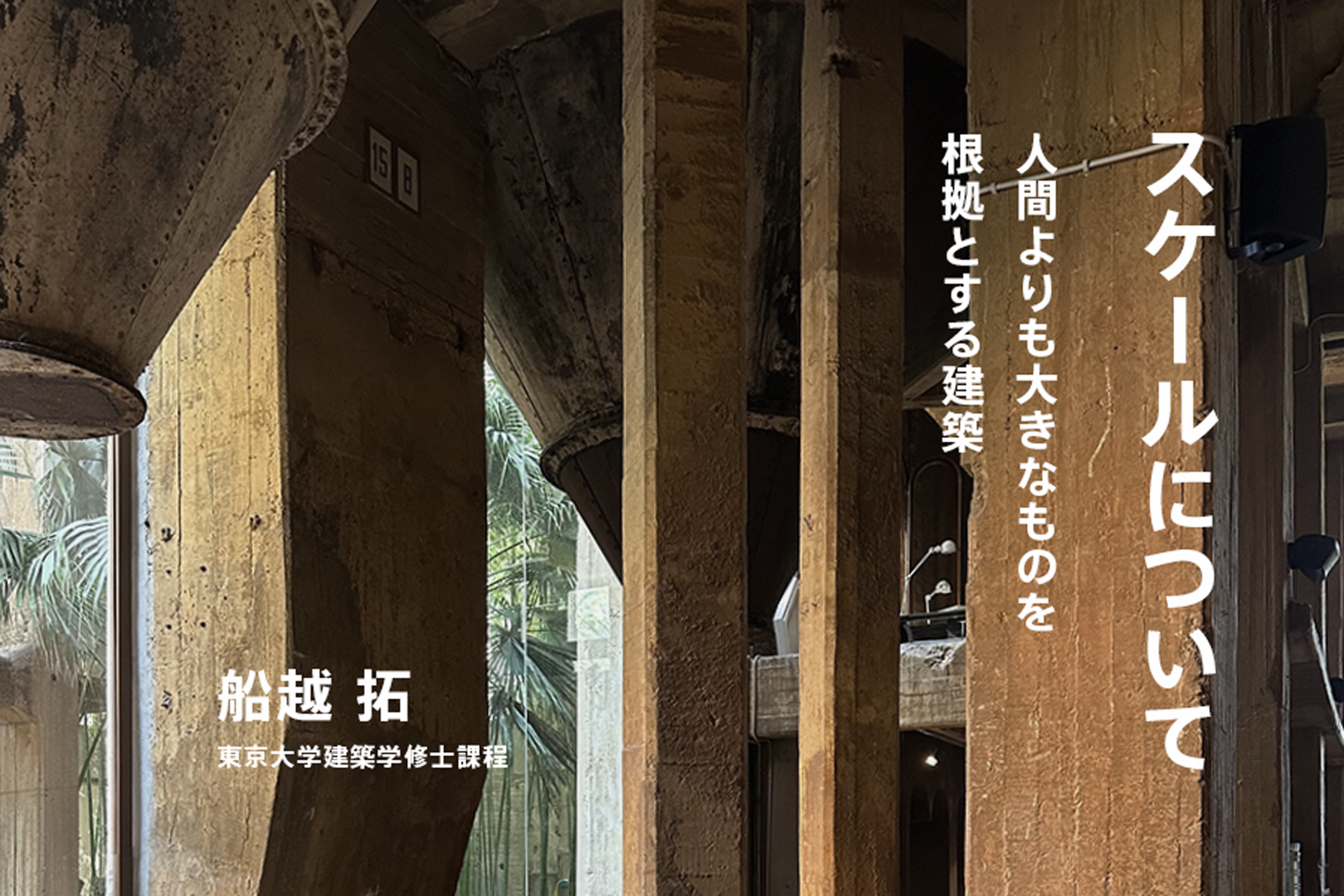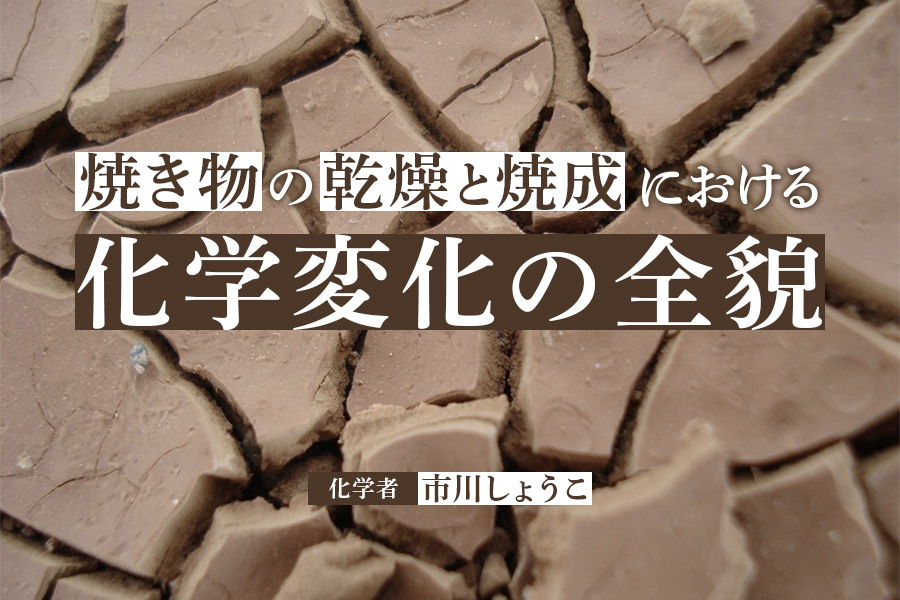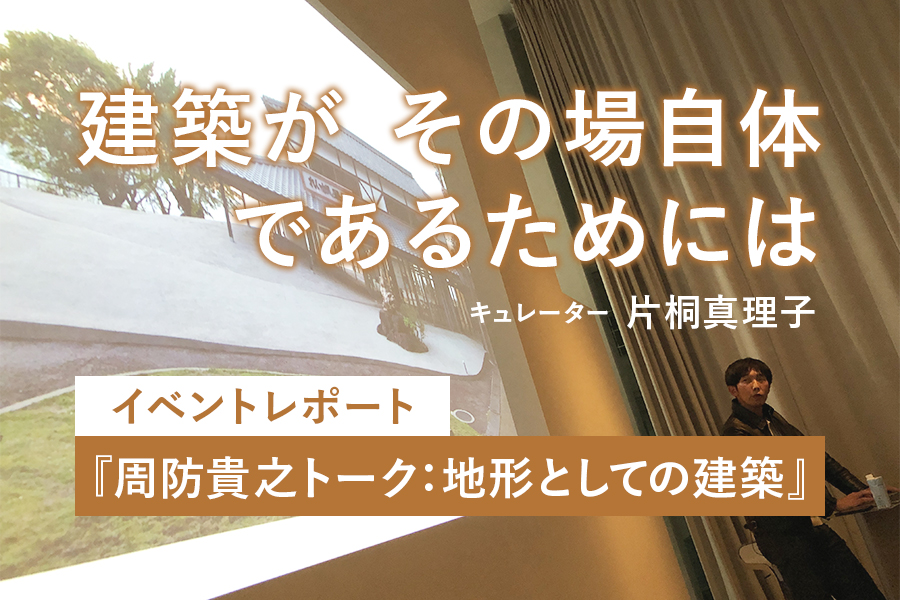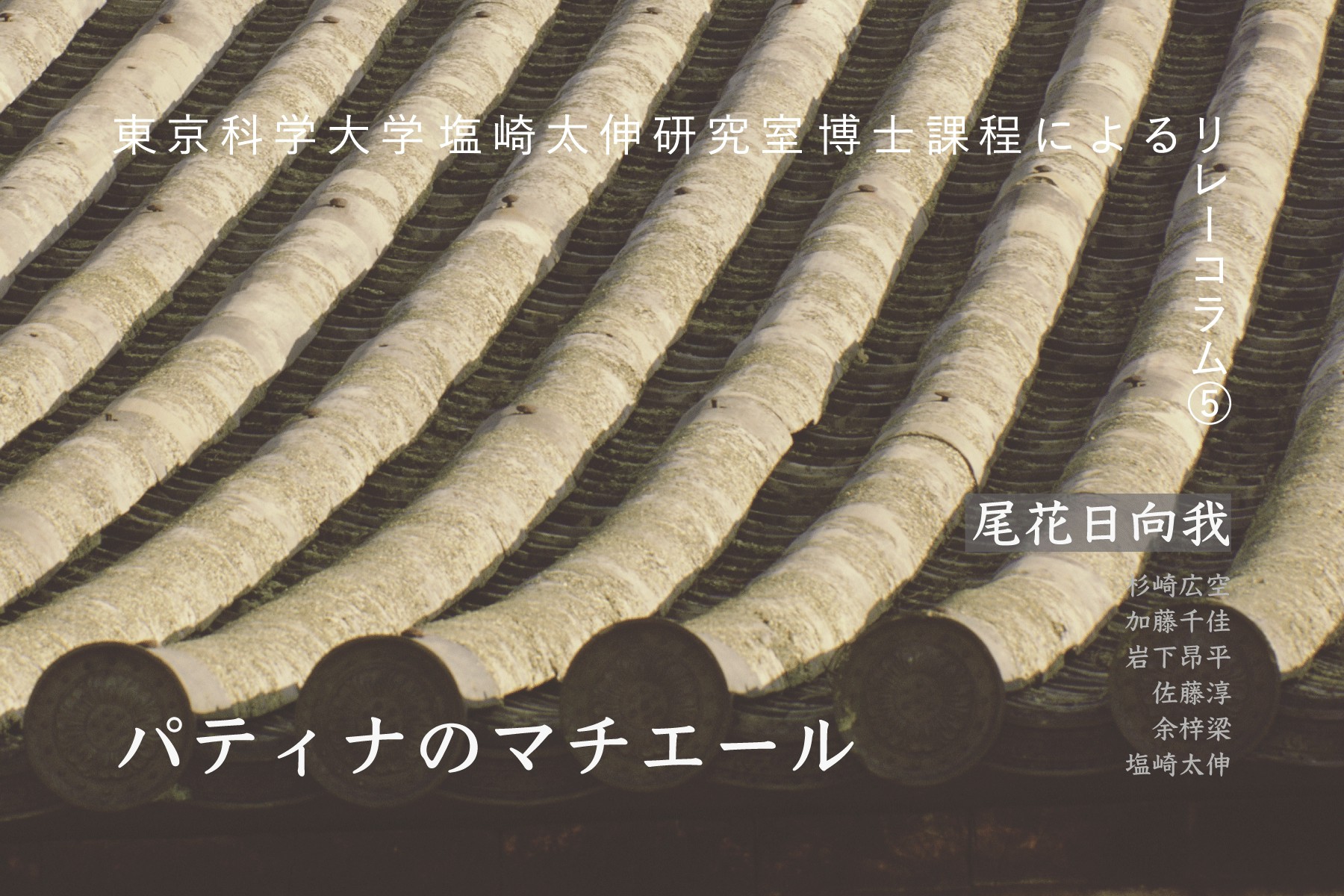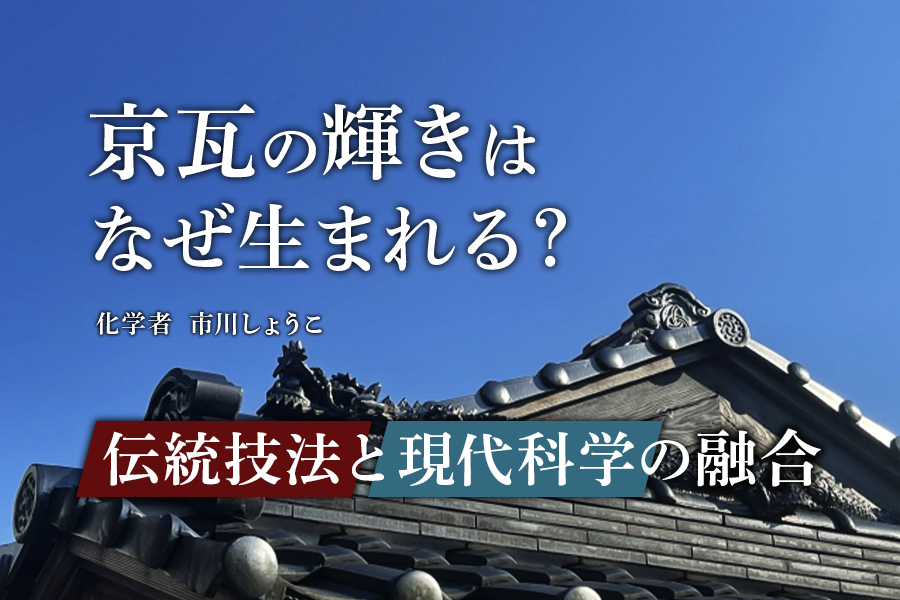素材を踏みしめて、まちを歩く(比護遥/日本女子大学大学院建築デザイン研究科 キャズ・T・ヨネダ研究室修士課程)

まちを歩く
私はまちを歩くことが好きだ。考えごとをしているとき、散歩を通して新しい気づきに出会える。そこで、私がずっと歩いていたいと思える、心地良い道について考えてみる。
例えば、石畳の道を歩くときは、なんとなくゆっくり歩きたくなる。都会のアスファルトの道路では、周囲の喧騒にのまれ、急ぎ足で歩かなければいけないという気持ちになってしまう。また、雨の日の石畳は匂いや音が変化し、街の雰囲気がガラッと変わる面白さがある。
地面を踏みしめて歩く私たちは、素材の違いを目でも足でも耳でも感じ取っている。つまり五感で知覚するまちの素材が、そのまちの表情をかたちづくっていると日々、感じている。
いろんな素材
都内を散歩していると、場所ごとに異なる素材がまちの印象を大きく左右していることに気づく。
歩道や路地の素材
渋谷スクランブル交差点は、歩行者や車が多く混沌としている。しかしその足元はアスファルトで整備されており、確かに歩きやすいが都市に画一性をもたらしている。
一方、表参道のけやき並木通りの歩道は石畳でできている。同じ都心の、人も車も多いエリアにもかかわらず、けやき並木の下でゆったりとした時間が流れているように感じる。

並木通りから一歩脇に入ると、路地には小さい店舗が並んでいる。そこでは、整備しきれていない凹凸のあるアスファルト、ガラスやタイル張りなどの店舗ファサード、そして緑が散りばめられていて、さまざまな素材が目に映る。
このような場所は、自然と散歩したいという気持ちが湧き上がってくる。歩みを進めるだけで、視界には異なる素材が入り込み、足元ではそれぞれの色や質感を踏みしめている自分に気づくのである。

商業空間
表参道と同じように高級ブランド店が建ち並ぶ銀座中央通りは、筆者にとっては少し近寄りがたさを感じるエリアだ。ガラス張りのショーウィンドウにはジュエリーやアパレルなどの新作が展示され、きらびやかな印象である。石畳の広い歩道を歩いてウィンドウショッピングをしていても、どこか忙しない空気が漂っているようにも感じる。なぜ、表参道と銀座は違った雰囲気を持つのだろうか。
銀座中央通りは緑が少なく、晴れの日は日光がガラスに反射してとても眩しい。雨の日はライトアップされたショーウィンドウが水たまりに映り込みキラキラしている。それに対して、表参道の並木通りはケヤキの緑がガラスのファサードにも反射し、落ち着いた雰囲気の中でウィンドウショッピングができる。晴れの日は木陰が日差しを遮ってくれて、雨の日はしっとりとした空気を醸し出している。
つまり、木々の影や緑の湿っぽさが「歩きたい気持ち」を後押ししてくれるのかもしれない。東京の街を歩くとき、目に入ってくる建物や植栽、舗装──それらすべてを、私たちは「素材」として無意識に感じ取っているのではないだろうか。
古き良き街並み
浅草には古来の寺社や伝統ある木造家屋が多い。石畳や砂利、アスファルト、木、漆喰など多様な色と質感の素材が存在している。なかでも、酒場の什器がアスファルトにあふれ出るように広がっているホッピー通りは、流れる時間や雰囲気がゆるんだような場所である。テーブルやパイプ椅子、半透明なビニールの仕切りが並び、雑多性を感じる。グラスがぶつかる音、焼き鳥の煙、揚げ物の匂い、威勢のいい呼び声、乾杯の音頭と笑い声── それらすべてが空間を成り立たせる素材の一部として感じられる。
この路地には、年季の入った看板がかかる店舗だけでなく、昔からあるのであろう住宅もひっそりと佇んでいる。建築に残る汚れやさび、そして人々の生活がにじみ出る街並みは、時間の流れを語っているようである。こういった場所は銀座や表参道とは対照的な雰囲気を持っているが、暮らしを感じさせる路地のあり方を提示してくれている。さまざまな素材の質感と、人々の営みが強く結びついていて、私たちは五感で賑わいを感じることができる。

夜の東京
六本木や表参道を代表とする、夜の東京の街は、街灯でギラギラと輝き、木々はイルミネーションに包まれ、ショーウィンドウやビルの照明が眩しい。オフィスビルに目を向けると、白い蛍光灯のもとで残業をする会社員の姿が見える。車道は何台もの車とライトで埋め尽くされ、飲み会終わりの人々の笑い声が交錯する。ガラス張りのビル群は、その賑やかな光景を鏡のように映し出す。

一方で、浅草の夜はまるで別の時間が流れているようだ。店舗の暖簾が片付けられると、それまでの喧騒とは打って変わって人通りが減り、静まり返る。路地を覗くと、ひっそりとお酒を嗜みながら語り合う人たち、家の中から聞こえるテレビの音や楽しそうな話し声、楽器の音色。店頭の提灯が木造の外壁を暖かいオレンジ色の光に照らし、訪れる人を包み込むような柔らかい印象を路地に放っている。

東京の夜は、昼間とはまるで違う表情を見せる。人々の営み、素材、そして光が混ざり合い、暗闇の中に浮き出るものがある。きらめくガラスも、温もりのある木も、街灯に掲げられた布の広告も、それぞれの場所で東京の夜を形づくっている。
素材がつくる街
東京のまちを歩いていると、素材の力強さに改めて気づかされる。どんな道路にも、どの建物にも、素材がある。私たちの意識は、それぞれの形や質感、街路樹、人々の営みや光も含めて素材として感じ取っている。
歩きたくなる道と、そうでない道。東京のまちにはさまざまな性格を持った場所があり、私たちはそれらを無意識に判断し、自分にとって心地良い経路を選んでいる。散歩の良いところは、ビルからまちを見下ろすときとは違った視点で、そこにあふれている素材を踏みしめ、そのまちの表情を読み解くことにある。
なんとなく足の向かう先に歩いていくと、思いがけない発見が待っている。