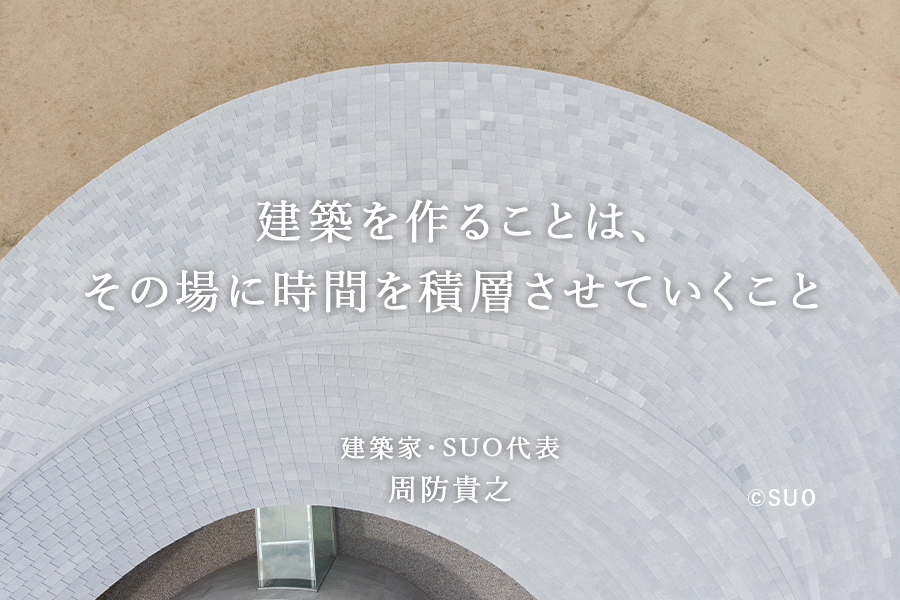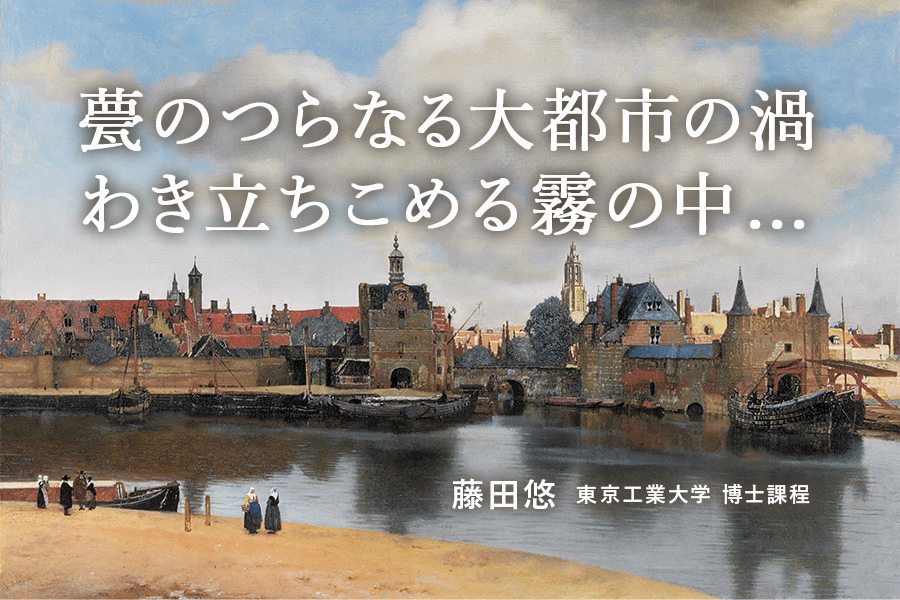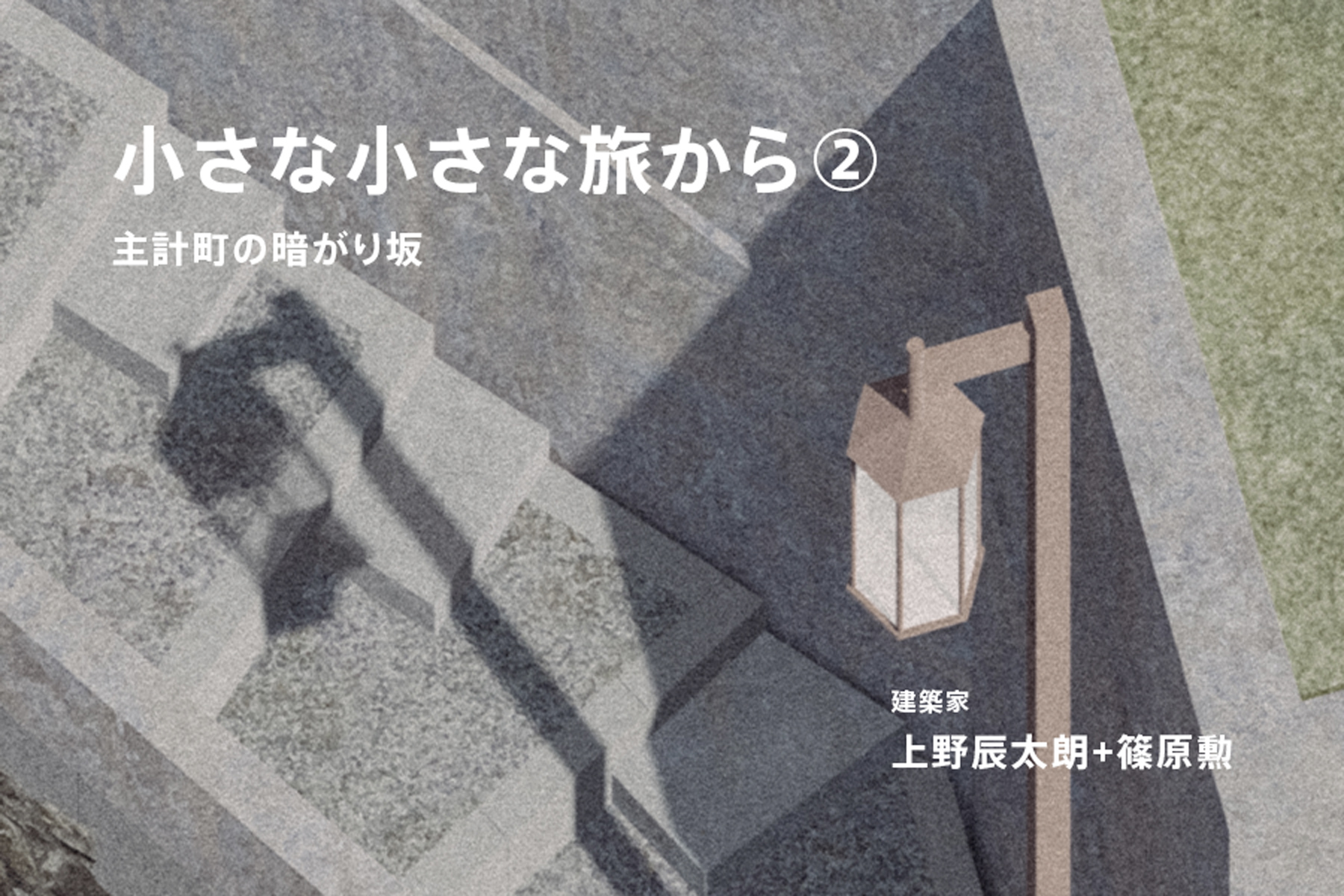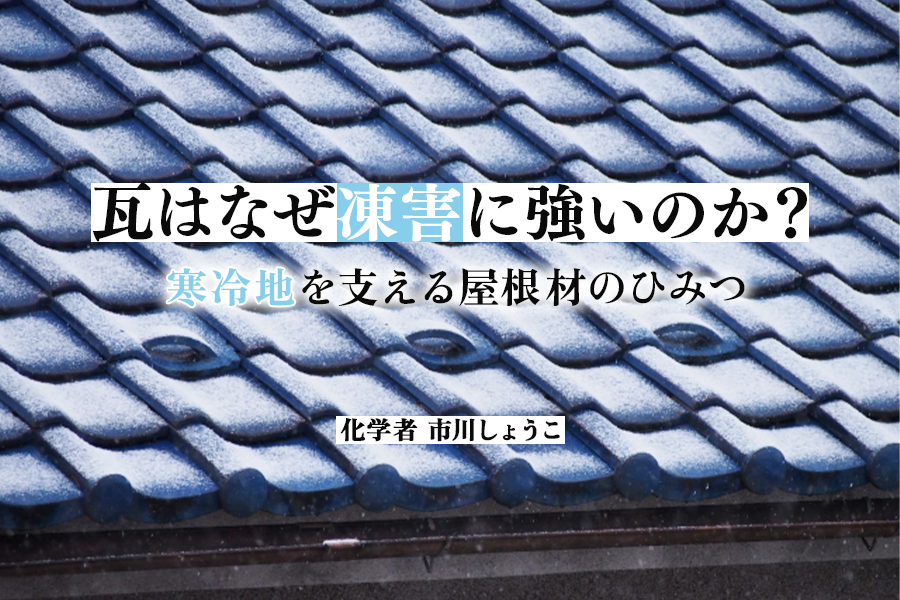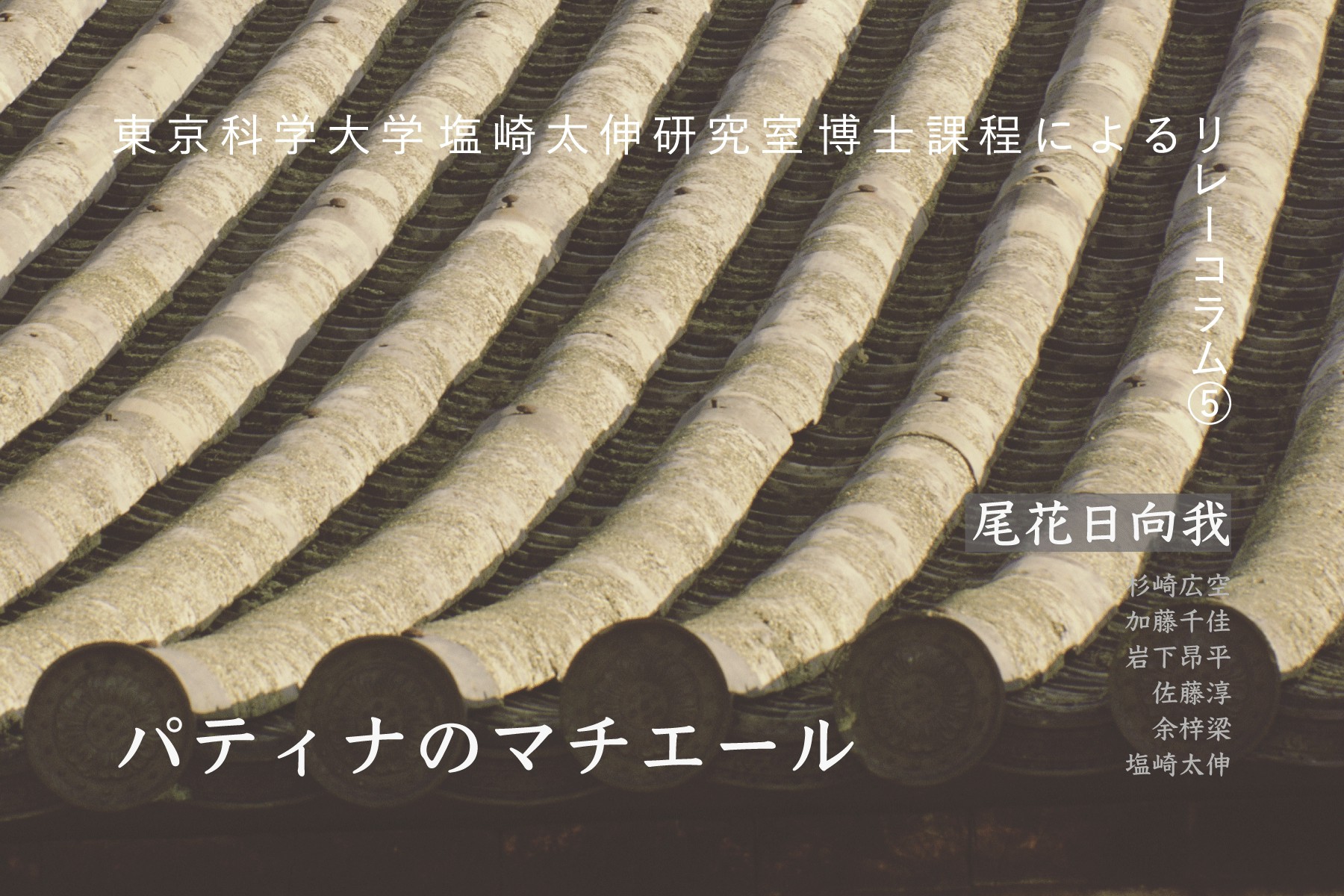レゴブロックは“建築的自律性”の夢を見るか? −組積研スタジオの挑戦−(片桐悠自/組積研スタジオ、東京都市大学)

ここ数年、“組積研(そせきけん, Soseki-ken, Stereotomic Laboratory)”というワーキングチームで、建築理論を可視化しようと試みている。ブロック玩具(レゴ®ブロック)を使って、建築批評をめざす試みだ。このところ「組積研スタジオ」として、設計活動も行っている。
発端は、2021年4月、筆者の本務先である東京都市大学大学院に、レゴの好きな谷田部僚太くん(当時、本学修士1年)がいたことだ。このときはまだ、「組積研」として谷田部くんと査読付き論文を書くとは思いもしなかった。
おそらく形になったのは、谷田部くんの修士論文が母体となって、2023年2月に展示会を行ったことだろう。この内容については、組積研で「抽象建築 Abstract Architecture」という理念を提示し、国際図学会誌Journal for Geometry and Graphicsに発表しているので、そちらを参照されたい。また、これまでの組積研の活動内容の詳細は、すでに2022-2024年度の日本建築学会学会の大会の連報として発表しているため、詳細は省くが、これまでの研究者としての生のなかで、不思議なスペクトラムをつくっている。
かつて筆者は、東大LEGO部として、ブロック玩具での「高解像度模型」の制作に携わってきた。
LEGO部創立メンバーの三井淳平さん、大村浩一さんらの薫陶を受けて、レゴ部2期生として入部できたのは僥倖だったのだろう。
大村さんが中心となって制作した「レゴ赤門」を手伝い、2年次より「ユータスくん(東大のマスコットキャラクター)」「レゴ駒場キャンパス(五月祭委員会60周年企画)」などの制作を任された。学部生時は、「レゴブロックで建築模型に勝負する”高解像度”」を目指し、1/1、1/40(レゴの人形の縮尺)、1/300(スカイツリーなどの大型のモニュメント)といったスケールを決めて、学園祭や外部イベント・番組依頼案件などに、自らの生を投じていた。
都市のモニュメントを、ブロック玩具でパスティーシュすること。
建築よりは、むしろ表現の生に興味があったのだと思う。
同時期に在籍していた東大建築学科で行われている表現に付帯する論理に、モダニズムの、古い社会改良主義の論理を全面に押し出したものが多いことに疑問をもった。SANAAに代表される「ネオ・モダン」というような風潮が、隆盛の2010年代前半である。スチレンボードによる”それらしい、今っぽいモダニズム”の模型は、学生のこころの底から発された創意ではなく、建築教育というシステムに強制されたおためごかしのように見えた。
学部1年時に田中純先生が講義された「美術論」を思い返す。講義ノートを読み返してみると、ウジェーヌ・アジェの写真、森山大道の「犬」、エティエンヌ・ルイ・ブレの「ニュートン記念堂」の、めくるめく建築たちが記されていた。「アルド・ロッシ『都市の建築』」もあった。
もう一度、アルド・ロッシに出会うこと。
朝早い1限、学部4年時に受けた岸田省吾先生の「建築意匠論」の講義だ。
ある日のスライドで、「セグラーテの噴水」が現れた衝撃。当時、学生皆がSANAAや藤本壮介、石上純也のような、複雑化したネオモダニズムのライトコピーを繰り返す2010年代頭のこと「この建築家は何を考えているのか」ということがずっと頭に離れなかった。
岸田先生曰く、「建築は見ないとわからない」
大学院に進み、パリ留学時には、ロッシの建築をいくつか見て回った。「セグラーテの噴水」は改修中だった。近づけない。だが、思ったより、でかい。
後に、何度かレゴブロックで、「セグラーテの噴水」を作ろうとした。難しい。一見、純粋幾何学の積み木を重ねただけに見えるのに、SANAAより難しいのではないか。なんどやっても目地が、円柱と三角噴水のあいだのチリなど、細かいディテールが気になってしまう。あの薄いコンクリートの板は何センチなのか。現状のレゴでつくる意味はあるのか。とりあえず、放棄してしまった。
そうしたなかで、修士(岸田先生は退任されたので、加藤耕一先生に教えを乞うた)で歴史系研究室に配属されたこともあり、文献研究にのめり込んでいった。つまり、アルド・ロッシの日記を追体験することだ。
彼の日記に入り込むこと。ロッシの建築、彼の故郷、彼の見たものを、イタリアに行きながら追体験するうちに、レゴブロックで再現しようとした記憶などはどこかに行って、その建築の本質はなにかということにのめり込んでいったのだとおもう。
組積研の活動は、そんな中から生まれた。
上野辰太朗撮影、2023年2月
建築的プロジェクトと人文学プロジェクトのあわいを目指すこと。制作を“建築的野球部(建築の職能集団)”に押し込めず、幅広い視野のなかから、あらゆるものを引き受けて、自らの生を変容するようなプロセスを形にすること。
モニュメント、記憶。死について。
組積研を始めたばかりのころ、谷田部くんが、小学生のときにレゴコンテストで入賞し、故・直江和由さん(レゴビルダー)に褒められたということをこっそり教えてくれた。修士1年のときに参列した、直江さんのお別れの会の記憶が、谷田部くんと結びついた。
おそらく、建築のオブジェクトのスケールを変化させるものとは、
誰かと誰かが、記憶のなかの旅を共有することなのだと思う。
組積研の活動は、「高解像度のレゴ模型」に対抗する。
「貧しいレゴ」だ。
わずかな、ディテールもない(ほとんどディテールすらも失った)、建築の組み合わせに、記憶が即物化される瞬間があるのではないか。ASB樹脂という、石に似た有機物の塊に、生を賭けるとするなら、石とも鉄ともレンガともRCとも異なる、子どもの身体と記憶に直接共有可能な手法が見出されるのではないか。
必要以上に、学生に負荷されたコンポジションと非対称への恐怖。
必要以上に、巨大化する課題提出用/コンペ提出用の模型。
必要以上に、求められる冗長な説明。
これらを批判するために、すべてを否定するがごとく、これらの”模型”はつくられた。
エレメントを仮構すること、
アブストラクトに、抽象化すること、
労働の共有、ブロック玩具で見る夢で見た塔のように、
もしかすると、詩的即融/参加(パルティシオン)が見つかるかもしれない。
最近、「レゴで建築をひらく」試みとして、建築コレクティヴGROUPとして“柱”をつくった。
天井まで届く高さの、“オーダー”だ。既存の梁に寄り添うように、差し込まれるように、立つや約1.8メートルと2.5の柱。
レゴの一種で、二倍の寸法をもつ「ディプロ」というブロックがある。ディプロを使うと、ワーカビリティが向上した。
ディプロは、より幼児向けの、飲み込む心配のほとんどない手のひらサイズが最小となる規格だ。施工の速度が上がったのは、「さらに低解像度の規格」で、身体の動きと柱の施工が一体になる感覚がもたらされたからだろうか。柱の軽量化も実現し、崩れた際のリスクも軽減された。
ブロックで作られた柱は、新しい家族として、生活に参入する。機能という人間の欲望をリテラルに反映した概念よりは、象徴という潜在的な願望を形にした「家の柱」である。もしかすると、ここから、人間の主体性とブロック玩具という”モノ”をを介した主体性の関係からなる生活の、新しい共同性が形づくられるかもしれない。