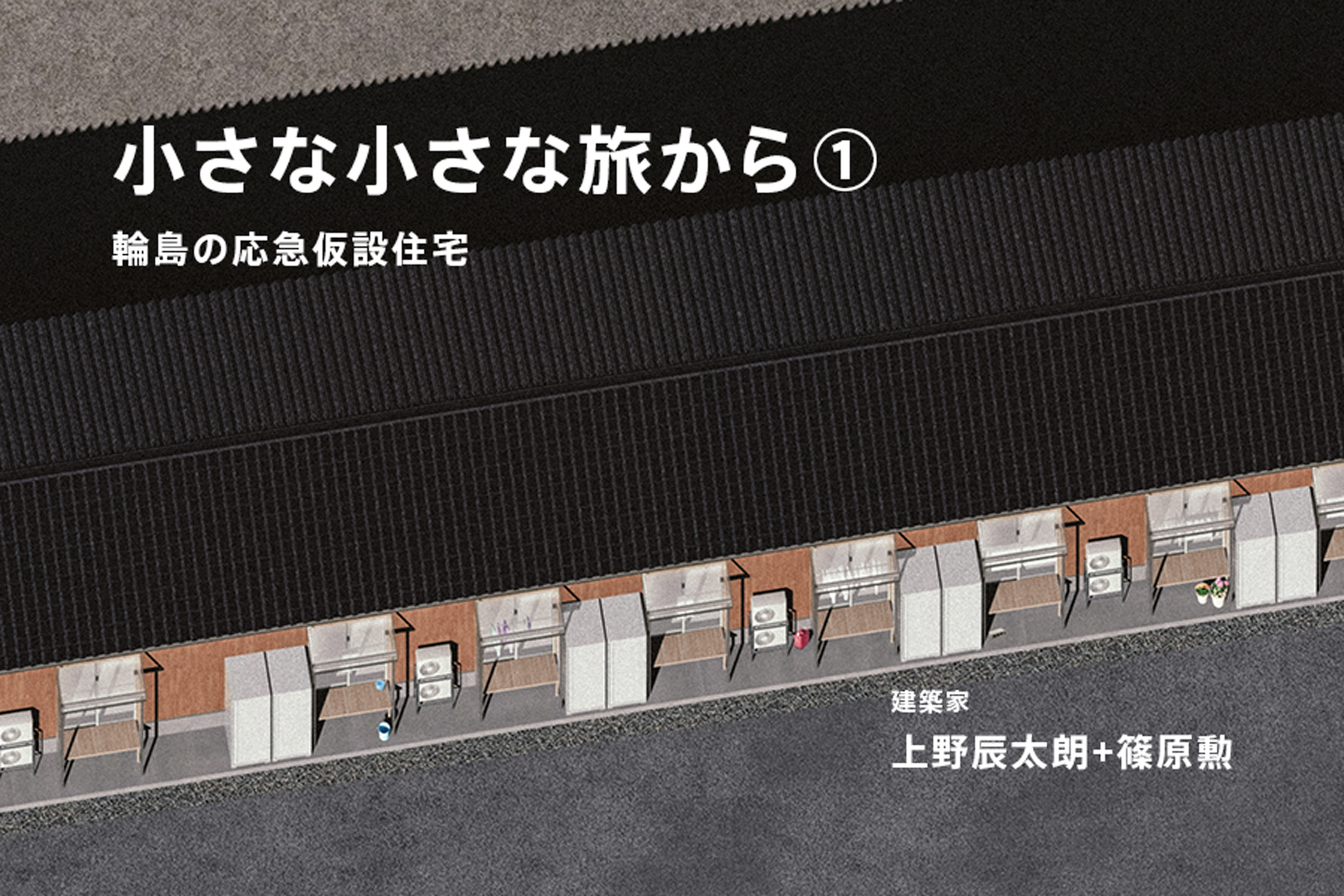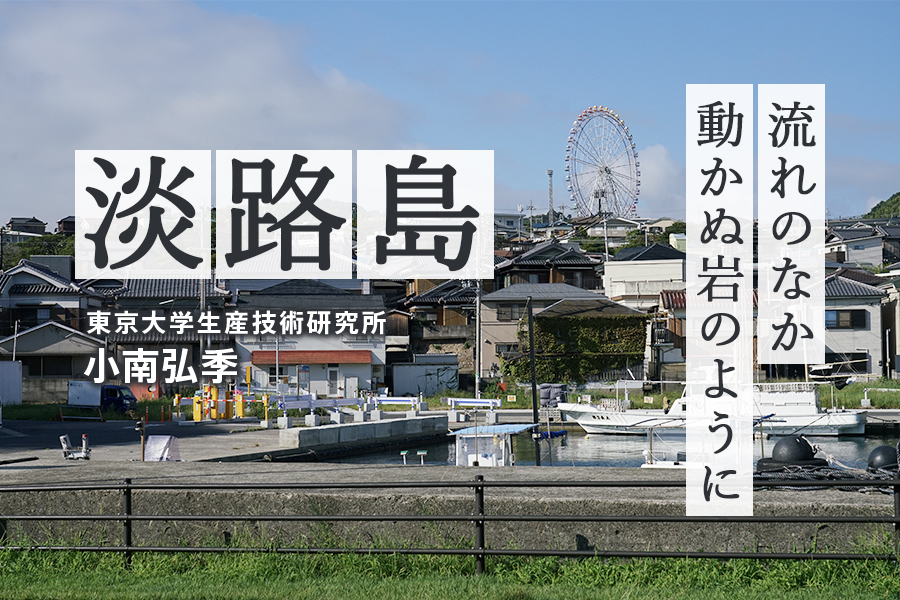建築行脚#01「旅立ち~ポルトガル」(御手洗 龍/建築家)
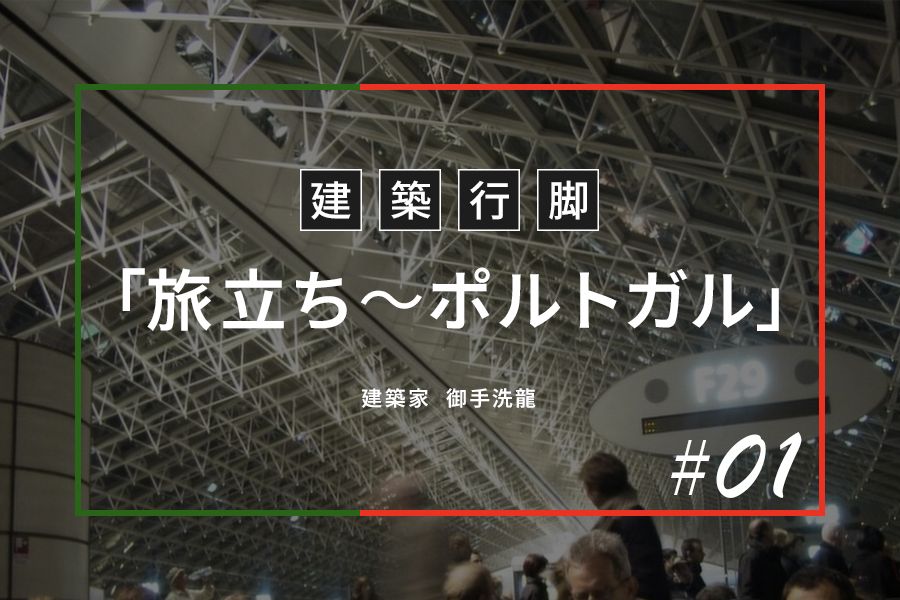
大学院生の頃、一人でバックパックの旅をしたことがある。3ヶ月かけて欧州11ヶ国を巡り、50都市を訪れ、270もの建築を浴びる建築行脚の旅であった。それが自分自身の建築観の大きな礎となっており、この旅で感じた記憶は今も鮮明に蘇る。

私の通っていた東京大学では、教養課程を経た学部2年生後期に、今までの試験の点数で進学できる学科が決まる「進学振り分け」という制度がある。恥ずかしながら希望していた建築学科に進むための点数が足らず、1年留年して取得単位を増やし、漸く建築学科に進学することができた。今思えば、こうして立ち止まって色々と考える時間は貴重で、自分にとって必要なことだったのかもしれない。
そして専門分野が始まると嵐のような日々が待っていた。他の大学が4年間で教えることを、この大学では2年半で教えなければならないのであるから、それは忙しい訳だ。ただ、私にとっては1年回り道をして漸く進学できた建築学科ということもあり、どんなに忙しくてもそのすべてがとても面白く夢中になれる日々であった。
このような嵐の中を駆け抜けていく上で、その最後に待っているのが、設計演習の集大成となる卒業設計である。それまでの演習であまり大きな評価を得ることはできなかったが、それでも自分の興味・関心に向き合い続け、夢中で取り組んだ。テーマも規模も用途も自由に決められるなか、古書街のある神田神保町に図書館を中心とした複合施設を計画し、実空間とデジタルの仮想空間を融合するという案を考えた。
苦しかった卒業論文の提出を終え、12月の初めに卒業設計が本格的に始動した。2月半ばの提出まで、寝るか食べるか設計するかの日々。その頃リリースされた宇多田ヒカルの「Traveling」という曲をとても気に入り、自分でもおかしくなるほど聴いていた。目が覚めた瞬間から寝落ちする瞬間まで、1日180回のエンドレスリピートという超ヘビーローテーションで再生していた。制作期間の2ヶ月半の間の再生数が1万3000回以上という計算となり、おそらく宇多田さん本人よりも聴いていたのではないかと思う。聴いていたというよりも浴びていたという感覚に近く、楽曲の世界観と自身の精神、設計行為が完全にシンクロしていた。
無我夢中でこの異常な状態の日々を駆け抜け、なんとか提出を終えるとその作品は学内で高く評価された。嬉しいことに、卒業設計最優秀賞である「辰野賞」と、安藤忠雄先生が設立した「コンドル賞(海外研修賞)」の両方を受賞することができた。私が初の受賞者となったコンドル賞は、100万円の賞金を渡航費、滞在生活費に充て、3ヶ月間、海外の設計事務所で実務経験を積むという趣旨のものであった。いくつかの事務所にコンタクトを取ったところ、「実務を経験するのには3ヶ月では短いので1年間来られないか」と言われたが、制度上難しく、大学に相談して賞金の使い道を建築視察旅行に変えさせてもらった。Travelingの曲を浴びて旅に出ることになり、ここでも仮想と現実がシンクロしたような感覚を覚えた。こうして私の建築行脚の旅が始まったのである。
パリのシャルル・ド・ゴール空港を経由して、2003年3月8日にポルトガルのリスボンに降り立った。久しぶりの飛行機で、さらに深夜のトランジットからそのままバスに揺られたということもあり、乗り物酔いで気分が少し悪かった。海沿いにある市内のバス停に夜明け前に到着して、そのまましばらく海辺のベンチで休んでいた。日が昇り始めて周りが明るくなった頃、近くでパステル・デ・ナタを売る声が聞こえてきた。日本ではエッグタルトと呼ばれており、リスボンで最も有名なスイーツのひとつだそうだ。とても美味しそうで、ふたつ購入した。甘く温かい焼きたての味に元気をもらった。
宿に荷物を預け、賑わいの出始めてきた街をてくてくと歩いていると、近くにエッフェル塔で有名なG.エッフェルが設計したエレベーターがあると聞いて行ってみた。後に調べたところによると、設計者はエッフェルではなく、その弟子のルイス・レイナルドのようだが、いずれにしてもその姿は独特だ。「サンタ・ジェスタのリフト」と呼ばれるその建築は周囲の建物から頭ひとつ抜けた程度の高さであるが、向こう側が透けており、各層にゴシックのような装飾が施されている。鉄製で頭が大きく、倒れやしないかと心配になる佇まいをしていた。


早速登ってみると、その景色に驚いた。旧市街の建物の屋根はどれもオレンジ色をしており、それが海や丘のほうまで広がっていたのである。この土地の粘土を焼いてつくられた洋瓦が自然とオレンジに近い赤褐色を帯びており、リスボンの美しい町並みを形成している。オレンジ色の屋根と屋根の間からは休日を思い思いに過ごす家族の姿が垣間見え、屋根の下の通りには賑やかに行き交う人々の姿が小さく見えた。この土地の土の色から建物の色ができ上がり、風景となる。そこに人々の営みが永く編み込まれてきたことを感じさせてくれた。

その後サン・ジョルジェ城を訪れ、旧市街を散策した。てくてくと歩いていると、起伏が多い土地であることに気が付く。街中を巡る細い路地には、地形に沿った形状の階段や曲がった道も多く、その狭い路地の中を時折り路面電車が走り抜けていく。リスボンの街は歩いているだけで風景がつぎつぎに変わっていき、そのひとつひとつが街角の風景として切り取られていて、とても楽しい。

家々が並ぶ狭い路地に迷い込んだときには、道に面した窓先に洗濯物が干されているだけでなく、建物と建物を繋つなぐように道を横断してロープが渡り、まるでガーラントのように洗濯物が干されている光景もあった。洗濯石鹸のいい香りが広がっており、街には香りというものがあるのだということを初めて感じた瞬間であった。
こうして3ヶ月に及ぶ建築行脚の旅はリスボンの街から始まった。