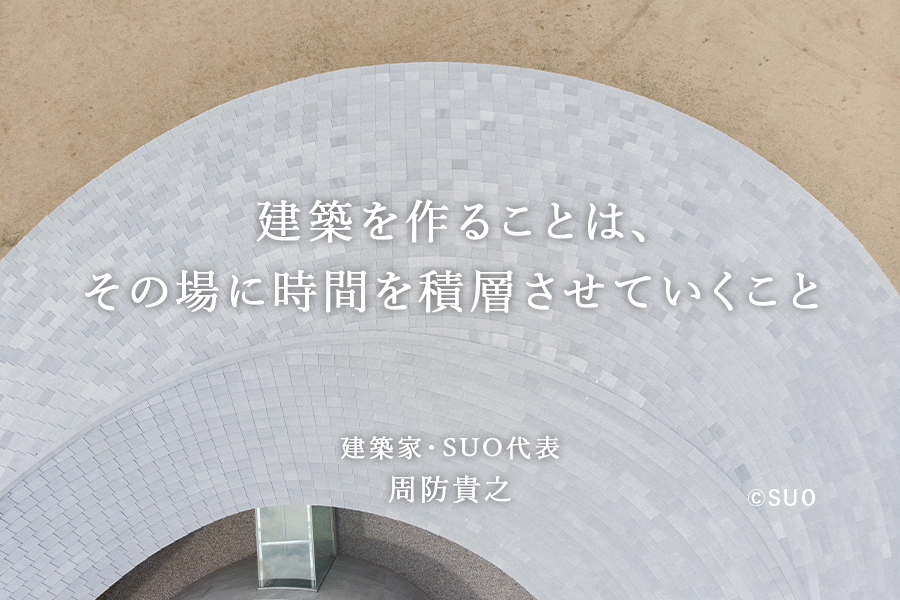建築の「皮膚」を読む。香川・高松で触れる、時を超えた素材の記憶(Sho建築士/一級建築士・動画クリエイター)

瀬戸内海に面した香川県高松市は、建築愛好家にとって特別な磁場を持つ街だ。丹下健三によるモダニズムの傑作から、現代建築家の野心作までがこの地に集積している。しかし、建築の魅力は「形」だけではない。その場所で何十年という雨風に耐え、人々の手に触れてきた建築の「皮膚(素材)」にこそ、雄弁な物語が宿っている。
今回、私は高松を訪れ、新旧の建築を「素材」という視点から読み解く旅に出た。コンクリート、石、木、そして金属。それぞれの建築家がその土地に何を選び、どう定着させようとしたのか。高松の建築群が語りかける、素材の対話に耳を傾けてみたい。
コンクリートに刻まれた「木」と「時間」
高松の建築を語るうえで、丹下健三の存在は欠かせない。解体が惜しまれる『旧香川県立体育館』(船の体育館)を前にした時、まず圧倒されるのはその質量感だ。吊り屋根構造によって船のように持ち上げられた巨大なコンクリートの造形。その表面は、単純な打ち放しではなく、スタッコなどの仕上げや補修の跡、そして半世紀以上の海風による風化が重なり合い、黄土色を帯びた「時間の蓄積」そのものの色をしていた。

一方で、同じく丹下健三が設計した『香川県庁舎』のエントランスには、異なるコンクリートの表情がある。柱や梁の表面に微かに浮かび上がる木目。これは板型枠を使用し、コンクリートに木のテクスチャを転写したものであろう。

近代的な素材でありながら、その表情は日本の伝統的な木造建築を思わせる。ル・コルビュジエのモデュロール(人体寸法に基づいた基準)を参照したとされるプロポーションと、木目の温かみを持つコンクリート。そこには、西洋のモダニズムと日本の伝統を融合させようとした当時の気迫が、素材のディテールとして刻印されている。

風景に溶け込む「繊細な」石と木
素材の選択は、その建築がいかに環境と調和するかを決定づける。
特別名勝・栗林公園にある茶室『掬月亭(きくげつてい)』の屋根で採用されているのは「杮葺き(※)」だ。一般的にサワラなどの木材をごく薄く割り、職人の手で何重にも重ねていくこの工法。瓦の重厚さとは対照的な、植物由来の軽やかさと繊細さがある。定期的な葺き替えを前提としたこの素材は、建築を庭園の一部として溶け込ませるための、先人たちの美学だろう。
(※こけら=「木」偏に「市」のような字を書くが、「市」の縦画が突き抜ける別字)

現代においてその精神を受け継ぐのが、谷口吉生設計の『東山魁夷せとうち美術館』だ。外壁に用いられた緑色の天然スレート(粘板岩)は、目の前に広がる瀬戸内の海の色や、周囲の木々と驚くほど調和している。通常は屋根に使われるスレートを壁面に積層させることで、石でありながら重さを感じさせず、東山魁夷の絵画のような静謐な空気を纏っていた。

圧倒的な「密度」と、研ぎ澄まされた「ライン」
時代ごとのエネルギーもまた、素材の扱い方に表れる。
バブル絶頂期の1988年に竣工した『瀬戸大橋記念館』は、ある種の「狂気」すら感じるほどの密度を持っている。荒々しい石積みとコンクリートによる要塞のような造形は、瀬戸大橋の開通を記念した博覧会のパビリオンとして建てられた当時の高揚感を、圧倒的な物量で今に伝えている。

対照的に、1991年竣工の『丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(MIMOCA)』に見られるのは、極限まで整理された素材の「快楽」だ。駅前広場に対してゲートのように開かれたファサード。コンクリートの壁面は、先端を薄く削ぐテーパー処理やシリカ系クリア塗装などの処理によって、まるで紙のような軽やかさを見せる。

特筆すべきは、コンクリートの目地と手すりの取り付け位置がミリ単位で整合されている点だ。異なる素材がぶつかる境界線を徹底的にコントロールすることで生まれる緊張感。そこには、建築家の美意識が細部にまで行き届いている。

金属の経年変化と、未来への被膜
素材は時と共に育つ。1966年竣工の『百十四銀行本店』の外壁を覆う銅板は、60年近い歳月を経て美しい緑青(ろくしょう)色へと変化していた。竣工時は赤銅(しゃくどう)色だった金属が、酸化して緑へと変わる。最新のガラス建築との対比のなかで、古びることが劣化ではなく「成熟」であることを、この緑青の肌が教えてくれる。

そして今、新しい素材の風景が生まれようとしている。2024年に竣工し、2025年2月に開館した『あなぶきアリーナ香川』(香川県立アリーナ)だ。SANAAの設計によるこの建築は、旧体育館の重厚さとは対照的に、雲のように低く広がる有機的な屋根を持つ。

塩害対策として採用されたフッ素樹脂塗装のステンレスパネルは、シーム溶接によって一体化され、高い防水性を確保している。継ぎ目を感じさせない金属の被膜が空を映し出す様は、まさに未来的な風景だ。

最後に訪れた屋島の『やしまーる』では、地域素材の再解釈に出会った。うねるようなガラスの回廊の屋根に葺かれているのは、3万枚以上の「庵治石(あじいし)」だ。土を焼いた瓦ではなく、高松特産の石を屋根に載せる。ガラスの透明感と石の重量感の対比は、伝統的な素材を用いながらも、全く新しい屋根のあり方を提示していた。


おわりに
高松を巡る旅は、単なる観光ではなく、建築の「皮膚」に触れる体験だった。
コンクリートの荒々しさ、石の静けさ、木の繊細さ、そして金属の滑らかさ。それらは単なる建材ではなく、その時代の技術、建築家の思想、そして地域風土との対話の結果としてそこに存在している。
時期やLCCのセールなどをうまく活用すれば、東京からでも往復1万円台でアクセスできるチャンスがあるこの街(※)。これほど豊かな「素材の博覧会」を体験できる場所はそう多くない。写真だけでは分からない、現地でしか感じ得ない「質感」を確かめに、ぜひ足を運んでみてほしい。
(※価格は時期・路線による)



-150x150.jpg)